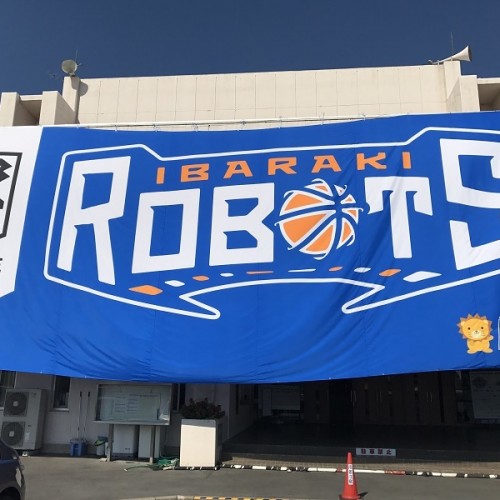『バスケ界がうらやましく見えた』 訪れた転機に挑戦を決意したわけ/サイバーダイン茨城ロボッツ社長 山谷拓志の歩んだ道筋 第2回

「茨城の誇りになりたい――」
2016年9月に開幕した新プロバスケットボールリーグ「Bリーグ」のサイバーダイン茨城ロボッツ代表取締役社長を務める、山谷拓志氏はそう口にする。
(写真: サイバーダイン茨城ロボッツ 代表取締役社長 山谷拓志氏)
昨シーズンはNBL(旧リーグ)で順位でも観客動員数でも最下位。2014年には経営悪化により破綻寸前まで陥ったこともある。だが、サイバーダイン茨城ロボッツが目指しているのは、2020-21シーズンまでにBリーグのチャンピオンになることだ。現状を見れば、決して容易ではない、それどころか不可能な目標のようにも思える。だが、最初から諦めるようなことはしたくないと山谷氏は言う。その高みに向かって妥協することなく挑戦する姿、そして強い姿を県民の人々に見てもらいたい、と。
茨城の出身ではない山谷氏が、なぜそこまでの情熱をサイバーダイン茨城ロボッツに注いでいるのか。「人生、山あり谷あり。名前の通りですね」と笑う山谷氏の半生を振り返りつつ、山谷氏がサイバーダイン茨城ロボッツに懸ける思いをひも解いていきたい。
(これまでの話)
第1回「『茨城の誇りになりたい!』 “のびしろ日本一”の地で見据える大きな夢」
■シーガルズ再出発
リクルートからの支援の打ち切りが決まり、残る3年で独立運営のクラブチームとして、再出発を図ることとなったシーガルズ。山谷氏は現役引退と会社の退職を決意し、アシスタントGMとしてチームの運営に携わることになった。
チームを継続させるためには当然、収入を確保する必要がある。それまでは運営費の100%をリクルートからの支援に頼っていたため、そこからは山谷氏自らもスポンサー営業やチケット販売、PRを行った。また、チームが強くないと注目も浴びないと考え、2年目以降はコーチも兼務するように。選手の指導をしながら、練習が終われば営業活動を行う、そんな日々を過ごしていたのだ。
それまで実業団チームとして運営されてきたチームを独立採算で運営するというのは、言葉でいうほど簡単なことではない。しかも3年間で、だ。なぜ山谷氏は、そんな困難を自ら引き受けたのだろうか?
「きっかけになったのは、サッカーですね。1998年に日本代表が初めてワールドカップに出場し、2002年には日本での開催が決まっていた。世の中のサッカー人気がものすごい高まりを見せている中で、アメフトが置いていかれてしまんじゃないかという危機感がすごくありました。アメフトをもっとメジャーにするためにはどうしたらいいのか、もっとスポーツのビジネス化が必要なんじゃないか、そういったことにもちょうど関心を持っていた時期でもあったんです。たまたまとはいえ、自分が所属しているチームが危機的な状況になった。だったらこの機会に、自分がスポーツチームをマネジメントする側の仕事に就こうと考えたのです」
今でこそ、“スポーツビジネス”、“スポーツマネジメント”という言葉がよく聞かれるようになり、大学や専門スクール、書籍などでも学べるようになったが、当時はまだそんな言葉すら無かったような時代だ。全てを手探りで進めていくしかなく、その苦労は多大なものだっただろう。また山谷氏はそのころ、並行して日本社会人アメフト協会(Xリーグ)の活性化推進委員も務めていたという。
「チームの仕事をやり始めてから、ある限界を感じるようになっていました。これは後に、バスケ界に入ってからも同じことを感じるようになるのですが、結局チームはリーグに参加しているわけなので、リーグ自体が有名で盛り上がっていないと、チームの人気を高めてお客さまを集めようと考えても、ある程度のところで限界が来てしまう。だから、リーグ側の仕事もしようと考えたのです」
当時、社会人協会がリーグの活性化プランの公募を行っていた。山谷氏はこれを好機と捉え、企画書を作成し応募したのだ。すると、何と大手広告代理店の案と山谷氏の案が最後まで残り、協会は最終的に両者の案を合併させてアメフト界の改革プランをつくり上げることになった。山谷氏は協会でプランの実行に向けた仕事をするようになったのだが、残念ながら各チームの反対に遭うなどの問題で、結局そのプランは実行されることなく終わってしまった。
そんな時、山谷氏のもとにある誘いが来る。リクルート時代の上司であり、組織人事コンサルティング企業であるリンクアンドモチベーションを創業した小笹芳央氏から、スポーツのコンサルティング部門を一緒につくらないかと声を掛けられたのだ。リンクアンドモチベーションでは、組織のモチベーションをどうマネジメントしていくかをテーマにしている。そこで、集団競技のチームづくりに対してノウハウを展開していき、同社が謳っているテーマを体現させていきたいという話だった。
「アメフトではチームもリーグも両方経験しましたが、なかなかマイナースポーツの域を超えて盛り上げるというところまではいかなかった。アメリカではあれだけ人気があるにもかかわらず、日本では人気がない。そのことに疑問を持つようになり、アメフトだけではなく他の競技も含めて、スポーツコンテンツの価値をいかに高めていくかが重要になるのではないかと考えるようになりましたね」
小笹氏と意気投合した山谷氏は、それまでにもシーガルズがオフシーズンの時には同社の仕事を手伝うこともあったが、シーガルズの方も独立運営のための基盤が出来上がっていたこともあり(後にオービックがメインスポンサーとなる)、正式にリンクアンドモチベーションに加わることになった。
■新たな挑戦、訪れた転機
同社では2004年末にスポーツマネジメント事業部門を立ち上げ、山谷氏はその事業部長を務めることになった。ここでは、リンクアンドモチベーションがさまざまな企業に対して提供している組織人事のコンサルティングや研修プログラムを、スポーツチーム向けに提供していくサービスを始めた。例えば、管理職研修をチームの監督・コーチ向けの研修へ、新人研修を選手向けの研修へとアレンジしたり、自分で自分のモチベーションをどう高めるかという研修をスポーツチーム向けにアレンジしたり、などだ。クライアントは順調に増加し、サッカー、野球、バレーボール、ラグビー、バスケットボールなど、さまざまな競技のチームや協会と契約し、強化等の支援を展開していく。
そんな山谷氏に、転機が訪れる。2006年の秋ごろだった。栃木でプロバスケットボールのチームを新たにつくるというプロジェクトが立ち上がっており、その社長に就任してほしいというオファーが舞い込んできたのだ。
「約2年ほど、スポーツマネジメントのコンサルタントをやってきましたが、どうも性に合っていなかったみたいです(笑)。というのは、アメフトで少しチーム経営をやっていたとはいえ、経営者としての経験は未熟でしたし、そんな自分が偉そうにコンサルティングするのも…、と。たまたまそのタイミングで社長就任のオファーが来たのです」
リンクアンドモチベーションとしても、自分たちの事業や提供してきたサービスの集大成としていつかは自分たちでチームをつくりたいという構想もあったことから、「おまえが社長をやって、日本一のチームをつくってきたらいい」という話になり、2007年から栃木ブレックス(現・リンク栃木ブレックス)の代表取締役社長を務めることになった。選手やコーチとしてバスケの経験が無かった中で、不安は無かったのだろうか?
「当時のバスケ界は、JBLとbjリーグという2つのリーグに分裂している状況ではありました。ただ、アメリカであれだけ人気があるスポーツですし、実は日本国内の競技人口は非常に多い。アメフト界にいた人間からすると非常にうらやましい競技だな、というのが正直な感想でした。ルールも分かりやすいですし、日本でも市場を拡大できる可能性は十分にあるのではないかと考え、非常に良いチャンスだなと思いましたね。
確かに競技経験は無いので細かい技術的な部分は分からないところがあるにしても、やはり同じ“スポーツ”をやっていたわけですので、選手の評価や契約なんかはできるだろうと特段気にしていなかったですね」
こうして栃木ブレックスの社長としてのキャリアをスタートさせた山谷氏。“奇跡”とも呼べるストーリーは、ここから始まったのだった。
————–
スポチュニティコラム編集部より:
サイバーダイン茨城ロボッツは現在、応援してくださる皆様からの支援を募集しています。
支援募集ページはこちら:
『茨城が誇れるチームに!バスケ日本一を目指すサイバーダイン茨城ロボッツを支援してください』
https://www.spportunity.com/ibaraki/team/151/detail/
1,000円から始められる支援、共感頂けた方はぜひ支援も宜しくお願いいたします。