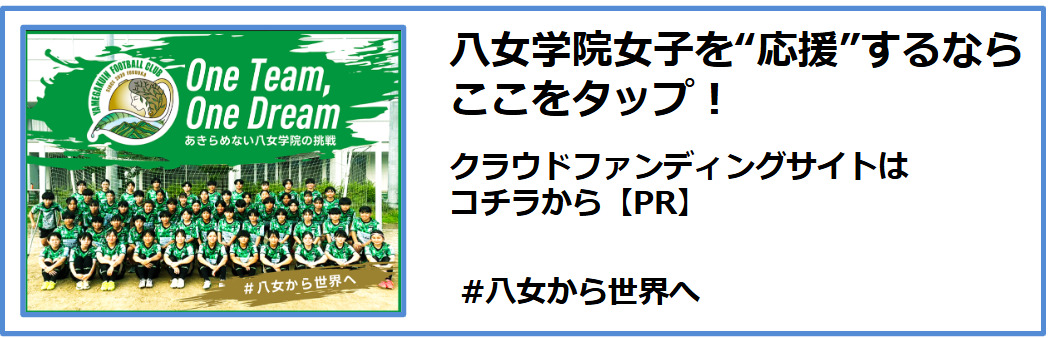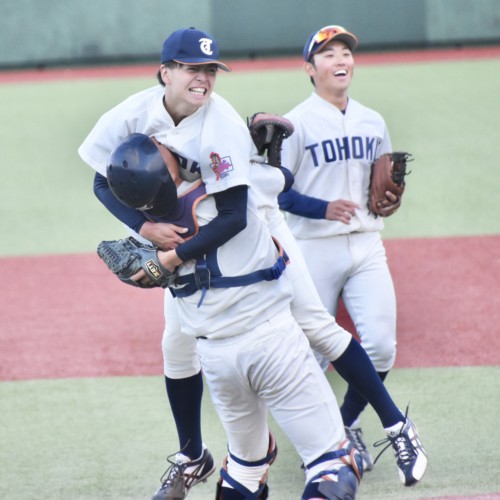八女学院女子フットボールクラブ「覚悟を希望に!!八女から世界へ!!」

八女学院女子フットボールクラブ(福岡県)が積極的に動いている。チーム運営者でもある樋口貴史監督が目指すのは、「全国、そして世界で活躍できるサッカー選手の育成」だ。
「全国や世界でプレーできる女子選手を地元・福岡、九州から育て上げることが、女子サッカー界全体の底上げにも繋がる」
樋口監督は明確なビジョンを持って、八女学院女子フットボールクラブ(以下八女学女FC)の舵取りを行っている。

「2011年に日本代表がW杯を獲り、女子サッカーが勢い付くと思った。しかし今では話題性も低くなり、世界ランク7位と順位も微妙な位置にあります。何よりも一番の問題点は、国内選手のプレー環境が整っていないこと。未来へのビジョンを持った改革が必要だと思いました」(ランクは7月2日時点)
国内トップカテゴリーのWEリーグも盛り上がっているとは言い難い。だからこそ「各地域が自立心を持ってレベルアップを図る」必要性を感じた。九州女子サッカー界の底上げに向けて動き続けている。
「九州では、なでしこリーグにヴィアマテラス宮崎(1部)がいます。しかし未だ十分には遠く、女子サッカー後進地域と言えます」
「八女学女FCでプレーする選手全員が九州出身です。福岡県は中学・高校年代から、関西や関東の強豪校へ越境留学の形で進学する選手もいます。そういった選手達が九州に残ってプレーできる環境を整えたい。そうすることで、九州女子サッカーのレベルも高まるはずです」

~九州の外へ足を運んで、日本中のサッカーに触れる必要がある
八女学女FCは2020年に発足、翌21年4月から活動が始まった。当初は中等部が地元の中学生が習い事感覚でも参加できるクラブ、そして高等部が学校主体の部活動の形態でスタートした。
「中等部をクラブ化にした理由は、女子選手の活躍できる場を広げてあげる目的でした。地元の中学に通い、習い事感覚でチーム練習に参加できるスタイルを作ることで、女子の選手が、中学年代でもサッカーを続けることができる環境を作る事でした」
「女子サッカーの普及が1番の目的なので、『クラブ生でやった後に県外へ行く』という選手がいても良いと思っていた。だから中等部は、『選手を幅広く受け入れて、週数日の練習参加』というクラブ形態でスタートしました」
「やっていくうちに現実的な方向性も見えてきました。中等部内でも部活動で毎日練習する選手と、クラブ選手との間で実力差が出てきました。結果、1年目の夏過ぎには全クラブ選手が自発的にクラブから離れ、中等部も部活動形態の選手だけが残りました」
選手の選択肢を増やす狙いもあり、当初は中等部と高等部で異なった形態を採用した。しかし時間と共に、部活動形態となっていったのが現状だ。
「フィールド上ですべきことは当初から変わりません。クラブ創設時に重視したのは、『外の世界を知って視野を広げる』こと。福岡や九州だけでプレーしていたら、全国や世界レベルを知れません」
「トップ選手の実力と自分自身の現在地を知らなければ、レベルアップできません。可能な限り九州外へ足を運び、ゲームを組もうと考えました。そのためにはチーム移動できるバスが必要でした」
樋口監督はチーム創設へ向け同学院に赴任すると、スポンサーからの協賛を募るために地域巡りを行った。集まったお金で最初に移動用マイクロバスを購入、自らがハンドルを握って全国を巡る日々だ。
「九州はもとより、中国や関西などもバスで行きます。新門司港(福岡県)からフェリーに乗って朝起きれば関西に到着するので、『関西は近いな(笑)』という感覚です」
「全国大会が行われる関東へも、フェリーに乗って横須賀(神奈川)などまで行きます。選手のコンディションを考えれば、大事な試合には飛行機や新幹線を使わせてあげたいのですが…」
野球のマイナーリーガーを思わせるバス移動で対外試合を重ね、チーム力は着実に上がっている。チーム理念への賛同者も増え、保護者会等の協力もあって、2025年度には2台目のバスもチームに加わった。

~九州のチームが全国舞台で結果を残すことが重要
八女学女FCの理念・ビジョンは、樋口監督のサッカー人生で培ってきたものがベースにある。Jリーグ・アビスパ福岡の下部組織に在籍、10代から多くの名選手たちとプレーしてきた。福岡大学へ進学後は、自らボールを蹴りつつ指導者への道も模索し始めた。
「九州以外への遠征を重視するのも、多くの選手・関係者と接してきた経験が大きいと思います。自分達の年代で多少サッカーができても、カテゴリーが上がればもっと上手い選手はいます。自分を磨き続ける必要性を常に実感してもらいたい」
10代ではアビスパ福岡U-15、18に所属、カテゴリーが上のトップチーム選手ともプレーした経験がある。
「Jリーグに出場するようなトップ選手は、技術、体力、精神力の全てが違うと感じました。『ああいう選手たちのようになりたい』と夢や目標をもらえました。刺激をいただき、モチベーションを上げてくれました」
大学進学後には現実を受け入れつつ将来についても考え始めた。「サッカー指導者として生きて行きたい」という思いを固め、各方面での指導を開始する。
「大学進学した時点でセカンドキャリアも考え始めました。中学時代に在籍した福岡ドリームズでのコーチ助手が最初の一歩。大学卒業後2年間は中学校の体育教諭をしましたが、その後はアビスパ福岡アカデミーコーチ等を12年間続けました」
アビスパ福岡時代の地域貢献活動として、福岡県や九州地区の女子トレセン(*)業務に関わった。その際にはナショナルトレセンスタッフも任され、全国の女子サッカーに触れることができた。(*トレセン:サッカー界での日本型発掘育成システム)
「福岡や九州はもちろん、関西、関東のチームや指導者を見ることができました。指導レベルの違いに愕然としたことを覚えています。指導方法や環境を整えないと、強豪チーム・地域との差は広がるばかりだと痛感しました」
「高校選手権上位校で九州出身選手もいます。活躍は嬉しい反面、『なぜ九州外へ出てしまったのか?』も考えるようになりました。また、九州の女子チームは全国大会で苦戦を強いられます。結果を残すことで、九州女子サッカー界のレベルが上がるはずです」
男子では国見高(長崎)や鹿児島実業(鹿児島)、東福岡高(福岡)などが全国大会で結果を残したことで、九州サッカー界のレベルが上がったと言われる。海外組を含めたプロ選手も数多く輩出するようになった。女子でも同様のことを目指していくつもりだ。
「有望選手が九州に残り始めてくれるなど、成果も少しずつ現れています」と、状況が好転し始めた手応えも感じつつある。

~フルコートとフットサルを並行してプレーできる環境
クラブ創設時に、「U-15(中等部)/18(高等部)で、2026年までに(5年で)“九州一”、2031年までに(10年で)“日本一”」を掲げた。U-15は2024年に九州王者となり、U-18は今季の皇后杯で福岡県代表の座を勝ち取るなど、結果も伴い始めている。
「高めの目標設定だったので、実現は五分五分だと思っていました。結果的にU-15は4年目に九州王者になりました。U-18は決勝で負けるなど、悔しい思いをしてきたのですが、腐らずに頑張って結果を出してくれました」
ゼロからのスタートだったが、地に足をつけ前向きに頑張ってきた中で結果も出始めている。「選手、関係者の誰もが本当に頑張ってくれています」と目を細める。そして、「フットサルでも2年連続で九州王者になっていることを褒めたいです」と続ける。
「フットサルも並行している学校は全国でも少ないと思います。今年度からは当校の選手がFリーグにも出場しています。フルコートとフットサルの両方で強化ができる。卒業後の進路選択にも幅ができると思います」

今年5月にFリーグ・ミネルバ宇部と連携協定を締結したことで、公式戦等への選手派遣が可能になった。選手個々の技術向上と共に、本拠地の地域活性化でもタッグを組めるようになった。
「フットサルに興味がある選手にはプレー機会を提供できます。実戦経験を積むことで選手は確実に上手くなります。女子サッカー・フットサル界のレベルアップに向け、新しいことに挑戦し続けたいと考えます」
ナショナルトレセンに関わった時期に、「方法を変えないと関東や関西に追い付けない」と痛感、動き出すことを決意した。「やるべきことは多いので、1つずつ着実にやるしかない。その中で形に残るものができていけば…」と付け加える。
「八女学女FCのフィロソフィーを作り上げたい。それを女子サッカー界全体で共有してみんなでレベルアップしたい。いわゆる“モデル校”的存在になれればと考えます」
女子サッカー界でも海外挑戦する選手が多くなっているが、その数がさらに増えれば日本代表もさらに強くなるはず。そのためにも足元である国内女子サッカーが強固であることが必要だ。

「福岡や九州のレベルを上げることが女子サッカー界全体の繁栄に繋がると信じています」
八女学院女子フットボールクラブのようなクラブが、日本女子サッカー界の底辺を支えている。今後の活動に注目すると共に、エールを送りたくなるクラブだ。
(取材/文・山岡則夫、取材協力/写真・八女学院女子フットボールクラブ、ミネルバ宇部)