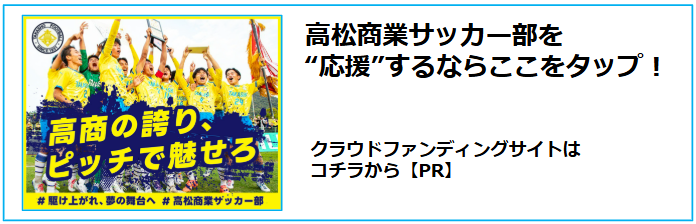高松商業サッカー部4年ぶり25回目の全国。あの日、立てなかった場所へ──OBコーチの想い

4年ぶりに全国高校サッカー選手権の舞台へ戻ってきた香川県立高松商業高校サッカー部(以下、高商)。今回の選手権出場は、実に25回目。この数字は香川県内最多であり、今回の選手権出場校の中でも5番目に多い数字だ。高商が長年にわたり県サッカー界の中心的存在であり続けてきた証明でもある。
しかし、数字が示す伝統とは裏腹に、近年の香川県代表の顔ぶれを見ると、その道のりは決して平坦ではなかった。直近の代表校の多くは私立高校が占め、公立校が全国への切符を掴む難易度は年々高まっている。指導環境、練習時間、設備面など、あらゆる条件で私立が優位に立つ近年において、選手たちの努力はもちろんのこと、チームを支え続けてきた保護者、そして世代を越えて母校に関わり続けてきたOBたちにとっても、この全国復帰は長年の悲願だった。

その象徴が、母校に戻りチームを支えてきたOBコーチの存在である。天雲大貴氏と梨野達也氏(ともに2011年卒)。高校時代、全国に届かなかった同級生の2人が、今は違う立場で再び全国への扉を押し開いた。その姿は、高商に関わるすべての人の想いが結実した結果にほかならない。
全国を目指して高商へ──天雲コーチと梨野コーチの原点
天雲コーチと梨野コーチは、小学生時代に同じクラブチームで汗を流した仲間だった。中学ではそれぞれ別のチームに進んだが、「高商で全国を目指す」という目標は共通しており、高校では再び同じ黄色のユニフォームに袖を通した。
当時の高商は、県内では安定した強さを誇っていたものの、全国大会にはあと一歩届かない時代だった。インターハイ予選は準優勝、選手権はベスト8。結果は決して悪い成績ではないが、目標にしていた舞台には立てなかった。その悔しさは、二人の中に長く残り続けた。
十数年の時を経て、天雲コーチはディフェンスラインを中心とした戦術面の指導者として、梨野コーチはフィジカルとメンタルを支えるトレーナーとして母校に戻った。OBで現監督の川原寅之亮氏(1992年卒)からの誘いがあった点も、大きなきっかけの一つだったと天雲コーチは語る。選手として叶わなかった全国大会出場を、後輩たちに託す。その覚悟が、今の高商を内側から支えている。

決勝戦直前の合宿が生んだ結束──「個」から「チーム」へ変わった瞬間
4年ぶりの選手権出場を語るうえで、決勝戦の直前に行われた一泊二日の合宿は欠かせない出来事だと二人は語る。
この合宿には、ベンチ入りの選手を中心に約30名が参加。梨野コーチと同じく、フィジカルやメンタル面でチームを支える赤山僚輔コーチがオーナーを務める繋安芯堂で行われた。ここはかつて宿坊として活用されていた古寺を改修した施設で、技術練習よりも、選手同士が向き合い、本音を言葉にする時間を重視した合宿だった。
普段の練習では言えない不満、焦り、期待、そして甘さ。学年も立場も関係なく、全員が包み隠さず言葉をぶつけ合った。その中で空気を大きく変えたのが、1年生のとある選手の発言だった。
「夏までは、自分がいかにいいプレーをするか、に集中していた。でも、3年生ともっと長くサッカーがしたい。だから、チームのためにできることをやりたい」。
この言葉は、学年の壁を一気に取り払った。上級生は責任を再確認し、下級生は自分の立ち位置を見つめ直した。チームが「勝つための集団」へと本当の意味で変わった瞬間だった。
この合宿以降、チームの結束は目に見えて強まった。

県大会の決勝戦で2点のリードを追いつかれた場面でも、誰一人として下を向かなかった。夏までの高商であれば、流れを失っていた可能性は高い。しかしこの日は違った。互いの想いを知り、信頼を築いていたからこそ、踏ん張り切れた。新人戦、インターハイ予選でともに敗れた、昨年の覇者・寒川高校の猛攻をしのぎ、PK戦で収めた勝利は、技術ではなく「結束」がもたらした結果だった。

フィジカルとメンタルの両立──梨野コーチが築いた勝負強さ
高校年代において、試合を分けるのは技術やフィジカルだけではない。むしろ、最後にものを言うのはメンタルの強さである。その点を強く意識してきたのが梨野コーチだった。
過去2年間、高商は終盤の失点に泣かされてきた。梨野コーチはその課題に対し、走力や体の使い方と同時に、「苦しいときにどう振る舞うか」を徹底的に選手たちに説いた。
選手同士が自然と声を掛け合う雰囲気が生まれ、誰かが苦しいときには必ず周囲が支える。けがで試合に出られない選手にも役割を与え、チームに必要な存在であることを伝え続けた。
その積み重ねが、2点差を追いつかれても動じない精神的な強さにつながった。フィジカルとメンタルを切り離さずに鍛えてきた成果が、勝負強さとして表れている。

番狂わせを起こすために──黄色の伝統を未来へつなぐ全国挑戦
初戦の相手は、今年のプリンスリーグ東北でも優勝した、福島県代表の尚志高校。高商が所属する香川県リーグの1つ上のカテゴリで優勝を収めており、格上の相手と言えるが、日々の練習では、「番狂わせを起こそう」という言葉が、自然と選手たちの口から出るようになっている。それは誰かに言わされたスローガンではない。積み上げてきた準備と、結束への確信が生んだチームの本音である。
高商は、40年以上にわたり地域の小学生年代の大会「高商カーニバル」を主催してきた。夏場は本来、県外遠征や強化合宿など、チーム力向上のために時間を使いたい時期である。それでも、その貴重な時間を割き、地域の子どもたちと触れ合う時間を大切にしてきた。憧れの黄色のユニフォームに初めて触れ、高商の選手たちを間近で見るその体験は、多くの小学生にとってサッカーの原点となっている。実際に、小学生時代に高商カーニバルに参加し、その後、高商に入学した選手はたくさん存在する。
この大会の継続を支えてきたのは、天雲コーチや梨野コーチといった現場に立つ指導者だけではない。代を重ねて母校を見守ってきた多くのOBたちが、運営、資金面、人的サポートなど、目に見えない部分で関わり続けてきた。
公立高校である高商は、私立高校のように潤沢な予算や専属スタッフを抱えることはできない。その不足を補ってきたのが、世代を超えて連なるOBの存在だった。
地元の子どもたちが憧れる存在であり続けること。それは、私立高校とは異なり、大半のメンバーが香川県内出身の選手で構成される高商サッカー部に課せられた宿命であり、責任でもある。
公立高校であるがゆえに、選手だけでなく監督も、サッカーに割ける時間は限られている。授業、進路指導、校務といった制約の中でグラウンドに顔が出せない日もあり、選手には自律が求められる環境にある。それでもなお高商カーニバルを続けてきたのは、勝利や結果だけでは測れない価値を、このチームが何よりも大切にしてきたからにほかならない。
地域に根ざし、次の世代に夢を渡す。その積み重ねがあるからこそ、高商が全国の舞台で戦う姿には特別な意味が宿る。黄色のユニフォームが憧れの象徴であり続けるために、高商サッカー部は多くのOBや地域のサッカー少年の想いを背負い、全国へ挑む。

(取材/文・真鍋智、取材協力/写真・高松商業高校サッカー部)