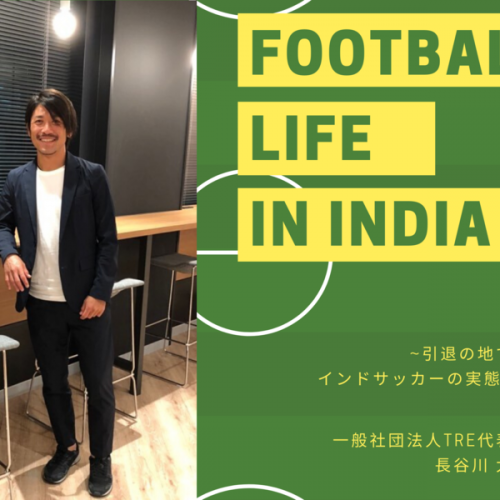いじめ後遺症の先でみた光――Jリーガー小川大貴、もうひとつのピッチ

深夜2時。授乳を終えたばかりの息子が、ようやく眠りについた。小川大貴は、テレビのリモコンに手を伸ばした。
NHKのドキュメンタリーが始まったばかりだった。小児病棟。画面に映る子どもの顔が、静寂の中で輝いて見えた。
「最期を迎えなくては、いけない」
ナレーションが流れる。病院に併設された施設で、家族が子どもを看取るシーンが映し出される。
涙が、頬を伝った。なぜだかわからない。ただただ、涙があふれた。
「こんな自分だけが、こんなに幸せでいいのか」
生まれたばかりの息子。プロとしての生活。叶えた夢。
コップから溢れるような幸せが、この瞬間、重荷に感じられた――。
(全2回の後編/前編はこちら)

幸せへの罪悪感
2016年初夏、小川大貴25歳。いじめを受けた過去を持つJリーガー。プロ3年目の、充実の時だった。
前年、大学時代から寄り添ってきた女性と籍を入れ、春には長男が産声を上げた。ピッチでも春にジュビロ磐田とプロA契約を結び、6月に前十字靭帯を負傷し離脱するまで先発の座をほぼ掌中にしていた。無念の長期離脱――だがその静かな季節は、己の現在地を見つめ直すための“臥薪”の時でもあった。
「こんな自分だけが、こんなに幸せでいいのか」
脳裏に、あの日々がよみがえった。
画鋲の椅子。踏まれたダウンジャケット。ベランダで撃たれたエアガン。クリスマスの教室で流した涙。いじめに苦しみ、自死すら考えていた自分が、気づけば、幸せの只中にいた。
ドキュメンタリーの中の子どもたちと、かつての自分が重なった。同じように辛い思いをしている子どもたち。
でも、今の自分は違う。幸せを抱えすぎている。
いじめで沁みついた「自分を第1に置けない」癖。その後遺症が、向きを変え、小川を突き動かした。
翌朝、小川はクラブの電話番号を押した。
「病院を訪ねたいんです――子どもたちに会わせてください」
その一言が、彼をピッチの外へと導く第一歩となった。

「サンタが来た夜」――初めての手ごたえ
初めての病院訪問は、奇しくもサンタクロースとして実現した。
「サンタさんが来たよ!」
子どもたちの歓声が、病棟に響く。
小川の胸には、あの日のクリスマスが重なっていた。
腫れた顔でサンタへの手紙を書いた少年時代。“特別な日なのに特別にならなかった”あの日。
病室で聖夜を迎える子どもたちの姿は、その記憶を鮮やかによみがえらせた。
袋からひとつずつプレゼントを取り出し、子どもたちに手渡す。
「自分はうまくできているのか?」
声をかけながらも、確信は持てなかった。
だが、帰り際――
「帰らないでー」
小さな指が、小川の手や腰をつかんだ。その感触に、ほんの少しだけ手ごたえを覚えた。
気づきもあった。付き添っている親たちの表情に刻まれた疲労、時間を奪われた暮らしの不自由さ。「自分が訪ねることで、少しでも気が紛れるかな」とも思った。
小川は、続けることを決めた。
ほどなく、旧友でジュビロ磐田のチームメイトでもある山田大記と活動を共にするようになる。同じ想いをもつ仲間の存在は、背中を大きく押した。
善意の活動が、動き始めた。
「ここにいるから、夢は諦めたんだ」
15施設目になっていた。
活動は順調だった。
クリスマスから始まった施設訪問は、やがて季節を問わない定期的な活動に発展していた。病院、児童養護施設――訪問先は雪だるま式に増えていた。
その日も、贈り物を渡し、子どもたちと笑いあう。児童養護施設への、いつもの“訪問”。
ふと、片隅でボールを蹴る少年が目に入る。
小川は自然に声をかけた。ありふれたやり取りのはずだった。
「将来は選手になりたい?サッカー選手が夢なの?」
「ううん」
少年は驚くほど静かな表情で続けた。
「ここにいるから、サッカー選手になる夢は諦めたんだ」
時が止まった。
頭を殴られたような衝撃だった。山田も同じ表情をしていた。
“夢を捨てた子ども”――その現実に初めて出会った瞬間だった。
プロを目指す仲間に囲まれて育った小川にとって、夢は追い続けるものだった。
しかし目の前の少年は、スタートラインさえ踏めずに夢を置いていた。
達観した瞳。環境を受け入れようとする諦念――。
小川は、この子の背負う事情を何ひとつ知らない。言葉にならない不条理だけが胸を刺し、背筋が冷えた。児童養護施設とは何か――それすら、自分は何も理解していなかった。「笑顔にできればいい」と軽く構え、訪れるたび満足していた自分に気づく。
軽すぎる考えだった。
帰りの車は、異様に静かだった。いつもなら、施設を出る時には話が弾む。子どもたちの笑顔。スタッフの感謝の言葉。手ごたえを語り合うのが常だった。
今日は違った。エンジン音だけが空気を削る。5分、10分――ただ続く沈黙。
「俺らって、訪問していることに意味あるのかな」
山田がぽつりと漏らす。
「……ないですね」
小川は即答した。
そこにあったのは、「自分たちの活動は、自己満足に過ぎない」という、乾いた現実だけだった。

解決にならない解決
“解決にならない解決”――
小川の脳裏に、別の記憶が浮かぶ。
会議室に並ぶ保護者と教員。別室での授業。先生による「仲よくね」という仲裁。相手の保護者が手にした菓子折り。
大人たちは自分たちの考えで動いていた。だが、儀式が終わるたびに戻ってくるのは、むき出しの現実だった。
なくならない画鋲の椅子。なくなり続ける上履き。消えないエアガンの痕。
解決に近づかぬ繰り返しと、”儀式”と現実の落差は、むしろ絶望と諦めを生んだ。
そして今、小川は同じ構図の上に立っていた。
プレゼントを配り、笑顔を作らせ、去る――「善意」という名の自己満足。根っこを見ずに背を向ける偽善。
いじめられていた自分が、今度は子どもの現実を“消費”している――。胸に走った衝撃は、かつての痛みより鋭かった。
車中の沈黙が続く。
でも、この沈黙の先に、何かがあるはずだった。本当に意味のある活動が。
小川と山田は、活動を根本から見直すことを決めた。単なる訪問ではない、本当の活動へ。
法人としての道が、そこから始まった。
まず〈知る〉ことから――本当の支援を求めて
小川はまず〈知る〉ことからやり直した。
子ども食堂を運営するNPO、シングルマザーの支援グループ、夜の学習支援──静岡の“居場所”を片端から巡り、そこで交わされる声に耳を澄ませた。
現場に足を運ぶと、見えてくるものがあった。家計の困窮と心の疲れ。親の孤立感と子どもへの不安。ひとつの問題が別の問題を生む構造。
支援は、点では届かない現実だった。
「思っていたより、ずっと難しいな」
山田と交わす会話も、以前とは変わっていた。かつてのような手ごたえを語り合う時間ではない。むしろ、自分たちの無力さを確認し合う作業に近かった。
「でも、やってみるしかない」
山田の言葉に、小川はうなずいた。
手探りの中、2023年に立ち上げた<ReFrame>(設立時一般社団法人、のちにNPO法人)。協働での子ども食堂から始まり、活動は着実に根を張っていった。それでも小川の心のどこかに、まだ〈足りない何か〉があった。
変化のきっかけは、病院での小さな出来事だった。
泥だらけのボールをめぐる、二人の子どもの小競り合い。
「うちの子のでしょう!」
母親が割って入り、片方の子どもからボールを奪い取る。その表情を、小川は知っていた。追い詰められた人間の顔。
「そんなので取り返しても嬉しくないよ」
息子の言葉に、母は顔をゆがめ、叫んだ。
「なによ、こんなもの!」
泥だらけの地面にボールを叩きつけ、泣き崩れる。
小川は何も言えなかった。子どもの苦しみ。親の苦しみ。そして、そうさせてしまう環境。
――子どもだけを見ていては駄目だ。
小川の中で、何かが崩れ、同時に新しい何かが立ち上がった。
“親も、環境も、まるごと支えなければ——”

自己満足を越えて――ReFrameが描く持続可能な支援
ReFrameの活動は、地域の企業、行政、市民を巻き込む仕組みづくりへと舵を切った。
発起人1,000人・1,000万円を初年度の目標に掲げた〈浜松こども基金〉の創設。常設・多機能型の拠点づくり。最終ビジョンは「ReFrameパーク」――子ども食堂と屋内グラウンドが隣り合う、“まちの心臓部”の実現だ。候補地の検討を進めている。
数名のボランティアで始まった小さな団体は、半年で延べ200名、50社以上を巻き込む渦となる。夏に開催した職業体験イベントは500人弱を集めた。支援は点から面へ、思いつきから構想へと姿を変えていく。
「情熱だけでは続かない。仕組みで回さないと」
気づけば、自己満足のステージは、もう過ぎていた。
支援を受ける側も、支える側も、ともに息が続く方法を——。
デスクの端から覗く、アンケートに記された文字。
“やめちゃってたけど、またはじめたよ”
あの日の車中、見失った行き先の輪郭は、少しずつはっきりとし始めていた。
競争を超えたピッチ
「いじめで出来上がった何かが、少しずつ、溶け始めているのかな」
最近の小川を見て、山田大記はそう感じていた。
小川には、相反するふたつの顔がある。
人懐っこく、相手の懐に飛び込み、すぐに打ち解ける“後輩キャラ”の顔。そして、心の奥では人を信じきれず、自分も晒さない、もうひとつの顔。その矛盾を、山田は長く見てきた。
だが、何かが変わり始めている。
小川は、ReFrameを「いちばんの居場所」と言う。
「次の打ち手」を語り合う、プロのロッカールームと子ども食堂後の食卓――似て非なる風景の違いを、身をもって知った。
ピッチでは味方であっても、同時に誰もがライバルだ。誰かが上がれば、誰かが下がる。友情の上に、薄い刃のような緊張が乗る。
一方で、ReFrameには勝者も敗者もない。評価や序列に縛られない関係性が、日常にあった。
小川にとって、それは新しいピッチだった。
競争ではなく協働を、勝利ではなく解決を目指す場所であり、プロとしての仮面を脱いでいい空間。
ここで小川は、長く閉ざしてきた扉を、少しずつ開け始めている。

行き止まりのピッチは続く――小川少年が見つけた居場所
いじめの後遺症は、完全には消えない。
無意識に周囲の温度を測り、視線に身構える癖は、今も体の奥に残っている。
小川はそれを受け入れたうえで、抱えたまま走ることを選んだ。
活動が動き出してからの小川を、盟友である山田大記は静かに見てきた。
“いじめがなかった別人にはなれないし、なる必要はない。経験が生んだ優しさと寄り添いを、そのまま活かせばいい”――山田はそう信じている。
他人の機微を読みすぎる癖。自分を第1に置けない習性。街中での過敏さ――まだ残るものは多い。それでも、氷は確かに薄くなり、陽が差し込む。
「自分の引っかかりに気づき、向き合ったことが、1歩目だったのかもしれないですね」
ピッチでの思わぬ突破、深夜2時のドキュメンタリー、沈黙の車中。
ざわつく自分を、静かに見つめ続けてきた。
その先に、今の1歩があった。
「取り除くことはできないですけど、うまく付き合いながら認知して、理解して、共に生きていく――そういうことだと思います」
行き止まりのピッチは、場所も仲間も名も変えて、今も続いている。
小川大貴の“生きなおし”は、今日も静かに、前へ進んでいる――。

(取材・文/沖サトシ)