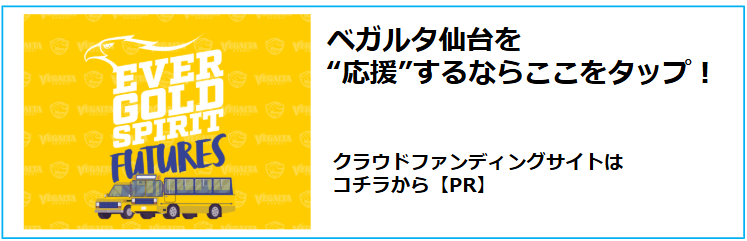黄金の循環が、未来を創る。ベガルタ仙台アカデミー、その揺るぎなき哲学とは

あの夏の確信
2025年真夏の夜空の下、決勝戦を戦い終えた選手たちがピッチに佇んでいた。日本クラブユースサッカー選手権、準優勝。頂点には一歩届かなかったが、その輝きは、今この瞬間の選手やスタッフだけが生み出したものではない。それは、何年も前にこのクラブの礎を築き、見えない場所で汗を流してきた幾多の指導者、選手、関係者たちの情熱が、時を経て結実した瞬間だった。
あの躍進は、決して一過性の奇跡ではない。過去から現在へと受け継がれてきた無数のバトンが、確かな光を放ったのだ。ベガルタ仙台(以下、ベガルタ)の未来を語る上で欠かせない「育成」という名の、壮大で、どこまでも愚直な物語について、2022年よりアカデミーダイレクターを務める山崎真氏に伺った。
その核心には、「循環」というキーワードがあった。

「魔法はない」だから、人を育てる
Jリーグクラブの下部組織として、トップチームで活躍できる選手を育てること。それが大命題であることは、他のクラブと変わりない。しかしベガルタがそれ以上に大切にしていることがある。それは「社会に出て活躍できる人材を育てること」。サッカー選手である前に、まず一人の人間としての成長を重視するからこそ、その先のカテゴリでの活躍が見えてくるものだとクラブは考えている。
「僕らが選手と接することができるのは、サッカーの時間だけ。だからこそ、その限られた時間の中で、ピッチの内外で『人としてどう振る舞うか』を伝え続けるんです」。山崎氏はそう語る。練習後のグラウンド整備やクラブハウスでの挨拶。サッカーの指導以上に、まず社会の一員としての基本が、ここでは説かれている。
「サッカーで学んだことを、違う畑に行っても生かして活躍できる人材に」。アカデミーを統括する山崎氏のこの言葉は、組織の哲学そのものだ。プロサッカー選手という夢を掴めるのは、ほんの一握り。だが、たとえその道が叶わなかったとしても、ベガルタで過ごした時間が、その先の人生の揺るぎない糧となるように。その信念が、すべての土台となっている。
「魔法はありませんよ」。
この言葉には、過去の苦悩が滲む。かつて、5年間もユースからトップ昇格選手を輩出できなかった冬の時代があった。山もあれば谷もある。右肩上がりの成長などあり得ない。その現実を知っているからこそ、かつての指導者たちがそうしてきたように、現ユース監督の加藤望氏も、目先の勝利や才能に一喜一憂せず、日々の練習で、ピッチの外での対話で、思春期を迎える世代の選手たちと愚直に向き合い続ける。その姿勢こそが、ベガルタの育成における唯一無二の「魔法」なのかもしれない。

世代を超え、熱が循環する場所
「今年の成果は、今の選手やスタッフだけの力ではありません。これまでアカデミーに関わってくれた全ての人の献身があったからこそです」。と山崎氏は語る。 この言葉こそ、ベガルタの育成を紐解く最大のキーワード「循環」を象徴している。
年に3回開催されるGKプロジェクトや、今シーズンから始まったアカデミースペトレは、まさにその循環を生み出す装置だ。GKプロジェクトでは、トップチームの選手がアカデミーの選手へ技術だけでなくプロとしての心構えを伝える。アカデミースペトレは、年代やフィジカル、テクニックのレベルが異なる選手が同じグラウンドで汗を流し、互いに刺激を得ることが狙いだ。これらの取り組みは、単なる技術指導の場ではない。先輩たちが築き、受け継いできた「ベガルタの魂」を、次の世代へと繋いでいくための大切な時間なのだ。
「OBがいつでも帰ってこられる場所に」。それは、この循環を未来永劫続けていくための、クラブの温かい理想像だ。その未来図は、まだ完成には至っていない。しかし、クラブユース選手権の決勝に多くのOBが応援に駆けつけたように、その萌芽は確かに見て取れる。
過去から現在へと受け継がれてきたバトンを、今度は未来へと繋いでいく。アカデミーを巣立った選手たちが、いつか指導者として、あるいはクラブスタッフとして、または単に元気な顔を見せるOBとして、この場所に戻ってくる。その循環が完成した時、クラブはさらに強固な「ファミリー」になるのだ。今期オープンした、東北学院大学泉キャンパス内の天然芝グラウンド「TGベガルタ仙台フィールド」やクラブハウスも、きっとそんな循環の中心地となるだろう。

「ベガルタ・グロウン50%」という、壮大な夢
「10年で10人のトップ選手を」。
2022年に掲げられたこの目標は、2024年に横山颯大のトップ昇格という形で、予想を超える早さで結実し始めており、過去の積み重ねの成果だと、山崎氏は語る。
そして今、クラブはさらに大きな夢を公言する。育成年代での指導経験が豊富な森山佳郎氏の監督就任を期に掲げる、「ベガルタ・グロウン50%」構想だ。
トップチーム登録選手の半数が、アカデミー出身者で占められる日。それは、単なる数字目標ではない。この街の子どもたちがベガルタのエンブレムを胸に、満員のユアテックスタジアム仙台のピッチで躍動する。それこそが、「地域に愛され必要とされるクラブ」の、最も幸福で、理想の姿ではないだろうか。
もちろん、その道は平坦ではない。だからこそ、まずは一人、そしてまた一人。ピッチ内外での対話を大切に、選手一人ひとりと向き合い続ける。一つひとつのマイルストーンをクリアしていく先に、壮大なビジョンは現実となる。

未来への入り口
その夢の入り口は、アカデミー傘下の「サッカースクール」にまでつながっている。宮城県内13校、月間約1,000人の子どもたちが、週末に「VEGALTA」のロゴが入ったウェアを着てボールを追いかける。
「サッカー、楽しい!」。
この純粋な感情が、すべての始まりだ。スクールでボールを蹴った少年が、やがてアカデミーの門を叩き、世代間の循環の中で磨かれ、トップチームの星となる。現に、堀田大暉、武田英寿、郷家友太、工藤蒼生も、その道を歩んできた一人だった。
ユース世代が見せたあの夏の一歩は、過去からの尊い贈り物であり、未来への希望に満ちた招待状だ。受け継がれ、つながり、そして巡っていくこの黄金の循環こそが、クラブを「本来いるべき場所」へと導いてくれる。杜の都・仙台で紡がれる物語は、これからも決して途切れることはない。

(取材/文・真鍋智、取材協力/写真・ベガルタ仙台)