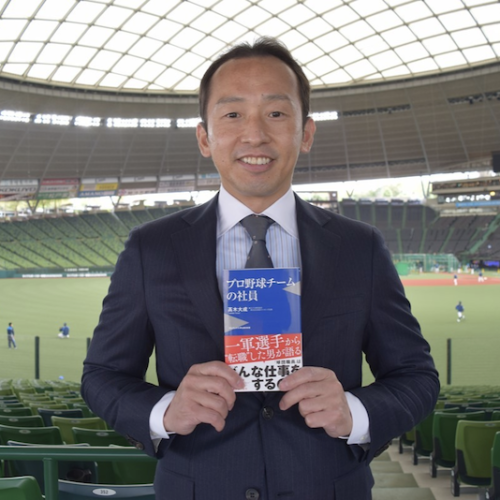日本の野球場の現状はどうなっているか?

広尾晃のBaseball Diversity
日本に野球が伝えられたのは1872(明治5)年のことだといわれる。アメリカ人の「お雇い外国人」ホーレス・ウィルソンが東京大学の前身である開成学校の学生たちに、野球の手ほどきをしたのが最初だといわれている。
戦前の野球場
この時期には野球専用の競技場はなかった。学生たちは学校の校庭で野球をしていたが、1878年、アメリカ帰りの鉄道技師、平岡凞が創設した日本初の野球チーム「新橋アスレチック倶楽部」が、今のJR品川駅付近に当たる品川八つ山下に「保健場」という名前の野球場を造った。これが最初の野球場だとされる。
その後、野球は大学生、学生を中心に人気スポーツとなったが、専用の野球場ではなく、依然として学校の校庭で試合をするのが一般的だった。
大学野球が盛んになると1902年には早稲田大学が戸塚球場、1903年には慶應義塾大学が三田綱町球場など、各大学が球場を建設するようになる。
1913年には、大阪府豊中市に豊中グラウンドができる。1915年に始まった全国中等学校優勝野球大会(のちの夏の甲子園)は、この豊中グラウンドで行われた。1916年に阪神電鉄が兵庫県西宮市に新球場を建設すると、大会は翌年からこの鳴尾球場で行われたが、観客が押し寄せたため主催者の朝日新聞社は、阪神電鉄に本格的な野球場の建設を要請。
これを受けて1924年、兵庫県西宮市に阪神甲子園球場が造られた。甲子園球場は中等学校野球(現在の高校野球)のために建設されたのだ。
1926年には明治神宮野球場が完成。この年から大学野球で使用されるようになる。
1936年には職業野球(プロ野球)リーグが始まると、この年に上井草球場、洲崎球場、翌年には後楽園球場が誕生した。
阪神電鉄と競合する阪急電車は1936年、職業野球参入を決め、翌1937年には西宮球場を建設した。
1930年代以降、野球人気の高まりとともに、各地に本格的な野球場が建設されたが、その多くは太平洋戦争で焼失した。

戦後の野球場
戦後すぐにアマチュア野球、プロ野球は再開され、各都市に多くの野球場が建設された。
プロ野球の本拠地では、1948年名古屋市にナゴヤ球場、1950年大阪市に大阪スタジアム、日本生命野球場、1962年、東京都に東京スタジアムが建設された。
1988年に開場した東京ドームは、これまでの日本の野球場の概念を一変させた。

日本初のドーム球場で、全天候で試合催行が可能になったことが大きいが、これに加え、球場サイズが両翼100m中堅122mと従来にない大きさだった。
公認野球規則では1958年6月1日以降に建設されたプロ野球チームが使う球場は、両翼325フィート(約99.058m)、中堅400フィート(約121.918m)以上が義務付けられていた。しかし、東京ドーム以前のプロ野球本拠地球場は両翼90m中堅110m程度で、規則を満たした球場はなかった。
東京ドームが初めて規則に適合した球場となった。これ以降に新造されたプロ野球本拠地球場は、両翼100m中堅122mがスタンダードになった。
また従来の球場も、両翼を拡げるなど大型化する改修工事を行った。
これまでNPBの本塁打記録は「小さな日本の球場で作られたもの」として、アメリカでは正当に評価されないことが多かったが、MLBの球場と同じサイズになったことで、以後NPB記録に対する認識は改められた。
その一方で、従来の都市型の球場は、大都市中心部の再開発などの影響を受けて次々と閉鎖し、新しい球場にとってかわられた。
最新の球場は「ボールパーク構想=野球場のテーマパーク化」によって人気を集めている。

プロ野球一軍本拠地(12)

現在の日本の主要な野球場をカテゴリーごとに紹介しよう。
()は所在都道府県と開場年
観客席は3万人以上、グラウンド、観客席の仕様も最上級で、日本の野球場の頂点に立つといってよい。東京ドームと明治神宮野球場を除いて、球団のグループ会社の所有か、球団が運営権を取得している。
セントラル・リーグ
東京ドーム(東京都1988)読売ジャイアンツ
阪神甲子園球場(兵庫県1925)阪神タイガース
※春夏の高校野球全国大会にも使用される
横浜スタジアム(神奈川県1977)横浜DeNAベイスターズ
マツダZOOMZOOMスタジアム(広島県2009)広島東洋カープ
明治神宮野球場(東京都1926)東京ヤクルトスワローズ
※東京六大学、東都大学野球などにも使用される
バンテリンドームナゴヤ(愛知県1997)中日ドラゴンズ
パシフィック・リーグ
みずほPayPayドーム(福岡県1993)福岡ソフトバンクホークス
エスコンフィールドHOKKAIDO(北海道2023)北海道日本ハムファイターズ
ZOZOマリンスタジアム(千葉県1990)千葉ロッテマリーンズ
楽天モバイルパーク宮城(宮城県1950)東北楽天ゴールデンイーグルス
京セラドーム大阪(大阪府1997)オリックス・バファローズ
ベルーナドーム(埼玉県1979)埼玉西武ライオンズ
なお、一昨年まで日本ハムの本拠地だった札幌ドーム(北海道2001)でも、野球の試合が行われている。
準本拠地 本拠地と同様球団が主催試合を行う球場
ほっともっとフィールド神戸(兵庫県1988)オリックス・バファローズ
埼玉県営大宮公園野球場(埼玉県1934)埼玉西武ライオンズ
二軍本拠地球場(14)

NPB12球団は、それぞれ二軍以下ファームの専用球場を所有している。観客席は小さいが、グラウンドの仕様は一軍同様であり、室内練習場、サブグラウンド、選手寮などを併設している。今年、巨人、阪神が新たな二軍本拠地球場を開場した。
またファーム・リーグに参加しているオイシックス新潟、くふうハヤテはそれぞれ公立の地方球場を本拠地にしている。
イースタン・リーグ
横須賀スタジアム(神奈川県1949)横浜DeNAベイスターズ
ジャイアンツタウンスタジアム(東京都2025)読売ジャイアンツ
昨年まで使用した読売ジャイアンツ球場(神奈川県1985)は三軍が使用している。また高校野球地方大会でも使用している。
CAR3219フィールド(埼玉県1979)埼玉西武ライオンズ
ファイターズ 鎌ケ谷スタジアム(千葉県1997)北海道日本ハムファイターズ
ヤクルト戸田球場(埼玉県1976)東京ヤクルトスワローズ
ロッテ浦和球場(埼玉県1989)千葉ロッテマリーンズ
森林どりスタジアム泉(宮城県2006)東北楽天ゴールデンイーグルス
HARD OFF ECOスタジアム新潟(新潟県2007)オイシックス新潟アルビレックス
ウエスタン・リーグ
タマホームスタジアム筑後(福岡県2016)福岡ソフトバンクホークス
ナゴヤ球場(愛知県1948)中日ドラゴンズ
1997年まで中日一軍の本拠地だった球場を改修して使用している
杉本商事バファローズスタジアム舞洲(大阪府2016)オリックス・バファローズ
日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎(兵庫県2025)阪神タイガース
広島東洋カープ由宇練習場(山口県1991)広島東洋カープ
ちゅ~るスタジアム清水(静岡県2005)くふうハヤテベンチャーズ静岡

地方の大型球場
上記以外に、3万人以上を収容できる地方球場
沖縄セルラースタジアム那覇(沖縄県1960)
福島県営あづま球場(福島県1986)
宇都宮清原球場(栃木県1988)
富山市民球場アルペンスタジアム(富山県1992)
倉敷マスカットスタジアム(岡山県1995)
長野オリンピックスタジアム(長野県1998)
坊っちゃんスタジアム(愛媛県2000)
ひなたサンマリンスタジアム宮崎(宮崎2001)
沖縄と宮崎の球場はプロ野球春季キャンプで使用されている。これらの球場はプロ野球の公式戦やオープン戦でも使用される。また2万人以上収容できる球場は約20ある。
これらの球場では高校野球、独立リーグなどの試合が行われている。
本拠地での動員が好調なため、プロ野球は地方での試合を減らし、本拠地球場での試合を増やしている。こうした地方球場は稼働率が落ちている。老朽化した球場もあるが、改修の予算の調達が厳しい球場もある。
「野球離れ」が進む中、地方球場は厳しい状況に置かれている。