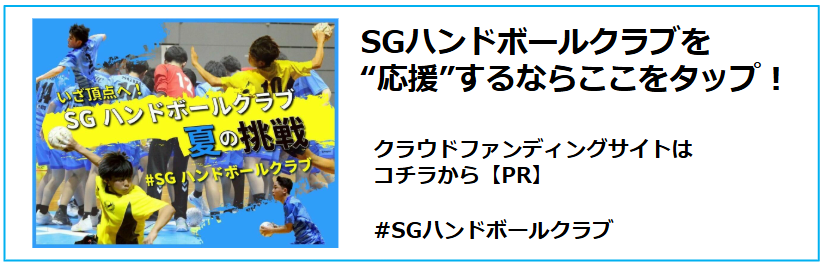“心を育てる”指導で全国中学生選手権へ! SGハンドボールクラブの挑戦

今夏岩手県で行われる全国中学生ハンドボールクラブカップへの出場を決めたSGハンドボールクラブ。2017年に兵庫県でクラブは誕生し、同大会には5回、春に行われる全国中学生ハンドボール選手権大会は3回の出場と創部9年で全国レベルといっても過言ではない実力を誇る。
ハンドボールは中学生から競技に触れる選手が多く、SGハンドボールクラブに所属する選手も多くが小学生では別のスポーツに励んでいた。経験者がいるチームが全国でも上位に進出する中、複数回全国大会に出場しているのは、米倉章弘監督が掲げる“個を伸ばす指導”と“心を育てる指導”が要因になっている。
発足当初は幾多の苦労も
世代別の日本代表選手を輩出
中学からハンドボールを始めた米倉監督。「サッカーをしたかったのですが中学に部がなく、似ているスポーツだった」ことが大きな理由だったが、進学した中学のハンドボール部が全国レベルだったことも入部の要因になった。
他のスポーツに比べ得点が多く入る魅力に惹かれ、その後も日本体育大学やドイツでもプレー。しかしケガの影響で現役を引退し、帰国後はハンドボールのスクールの開校を決めた。
ただ「何とかなる」と楽観的な性格の米倉監督をもってしても、発足当初は苦労の連続だった。
先述の通り、小学生ではハンドボールに触れる機会は少なく、部活動がある中学もそこまで多くない。小学生から活動しているチームも、そのまま中学のクラブチームで活動することが大半だ。
そこで米倉監督の恩師で、国内では第一人者である宮﨑大輔氏を指導した冨松秋實氏を招き、単発のハンドボールスクールを実施。約150名が集まり、今後の運営に向けて好材料になるはずだった。
しかしその後は活動場所の確保に苦慮。他のスポーツとの兼ね合いで、なかなか練習できる場所が確保できなかった。
さまざまなネットワークを利用して何とか場所が取れるようになっても、次は参加者がいない問題に直面。ホームページやブログで情報発信をしたものの、練習に1人も来なかったことが何度もあった。
その中でも米倉監督の指導に賛同し、コンスタントに参加していた選手が住んでいた地域に活動拠点を移すと少しずつ部員が増加。移動先の保護者の協力もあり、練習場所を固定化することができた。
1年目は小学生を含めた4選手での活動となったが、その後は保護者や選手たちも“選手勧誘”をサポートし、試合に出場できるまでになった。
当時から一貫しているのが“個を伸ばす指導”だ。チームの人数が少ない頃から、「将来全日本を目指せるような選手作りを目指す。
その考えを持つようになったのは、現役時代を過ごしたドイツでさまざまなチームを見た経験からだ。当時ドイツは世界トップクラスのレベルを誇り、個人能力の高さが際立っていた。「いい組織については先々でいくらでも学べるので、それよりは例えばものすごいシュートを打てるとか、ものすごく1対1が強いとか。個人の能力に長けた選手が、将来代表に絡める選手なのでは?と思っていました」と米倉監督。
保護者や選手から日本一を求められることは当然あるが、一定の勝利を目指しながらも将来を見据えて個で打開する力は求められるというのが米倉監督の考え。カテゴリーが上がれば自然と組織力は養われるため、まだ色に染まっていない中学でこそ個の力を大事にしている。
「日本一を取ろうと思ったら、組織的な練習をすればいいと思います。でもうちではそういった練習は少ない。」と米倉監督。
その結果、すでに世代別の日本代表選手、候補選手を複数輩出。個を伸ばす指導が実を結んでいると言えるだろう。

取り組む姿勢と考える力を養い、
心の成長を促す
一方、メンタル面でも“心を育てる指導”で、個の力を伸ばしている。
「結果ではなく、取り組む姿勢に対しては厳しくしています。全力でやって駄目ならしょうがないです」と米倉監督は話す。
部員の勧誘もその延長で、「一生懸命声をかけて誰も来なかったとしても構わない。好きなことをするには嫌なこともしないといけないし、今この場でそうしたことを学んでほしい」と、経験の意味で選手たちの協力を仰いでいる。
また、米倉監督はあえて選手たちに実戦形式のメンバー構成や練習メニューを考えさせることがある。選手たちも「何となく」決めるのではなく、選手同士の相性や今の課題を考えており明確な理由を持っている。
「例えば大会に出ても、何が何でも優勝ということはありません。優勝を狙うと子どもたちの個性を潰して、自分の理論ハンドボールっていうのを全て綺麗に押し付けようとしてしまう。やはり中学生の世代は自分で考えることが大事。それがうちのハンドボールです」
その指導の成功例が5月に行われた全国中学生ハンドボールクラブカップ2025近畿ブロック予選。米倉監督は「勝っても負けても後悔しないように練習をしなさい」とだけ選手たちに伝え、大会前の2週間は練習を見守るだけで、最終調整を選手たちだけでこなした。
迎えた大会本番。決勝まで勝ち進むと、小学生時に全国2位になったメンバーがそのまま進学したクラブチームとの対戦になった。中学から競技を始めた選手が多いSGハンドボールクラブとでは経験や組織力の差があったが、勝利を挙げ見事近畿の頂点に輝いたのだ。
「見守るということに誤解される方もいます。でもやらされているのではなく、自分たちで取り組んで勝ったことは自信につながります。なおのこと今回は実績のあるチームに勝ったので」と米倉監督の想定以上の収穫があったという。
当然主体性を持てるまでは米倉監督の指導が入る。そして勝利後は「天狗になったのか低迷期に入ってしまいました」と檄を飛ばしながらの指導に。このアメとムチもまた、選手たちの心が育つ要因になっている。
取り組む姿勢を大事にしながら、考える力を養う。これが“心を育てる指導”で、SGハンドボールクラブの大きな柱になっている。

ベストパフォーマンスの先に見据える
全国優勝の景色
個性を大事にする方針で、チームやOB・OGの結果も出始めている。今後も人間形成を目標に、指導を続けていく。
「チームではなく人を育てていきたいと思います。物事の良し悪しをわかるようになってほしいので、だからこそ自分で考えるようにしています」と米倉監督。
8月に控える全国クラブカップでも「優勝はもちろん目指しますが、目標はベストパフォーマンスを出すこと。やってきたことを全て吐き出せるように頑張ってほしい」と掲げている。
春の選手権大会ではベスト16で敗戦し、結果でも内容でも悔いが残った。
それでもこの敗戦以降は個々の成長が見られ、近畿大会の優勝に加えて、主力を欠きながら春の選手権大会で優勝したチームに練習試合で勝利。ベストパフォーマンス=全国優勝という立ち位置にいる。
「本番の緊張感の中でどれだけ自分たちの力を出せるかが鍵になると思います」と米倉監督は大会を見据えている。
自分たちの力をいかに出せるかということは、自分たちの意識が重要になる。心を鍛えているSGハンドボールクラブにとって、いかなる時でもベストパフォーマンスを出せることは、たとえ優勝できなくてもチームとしては合格点に値する。
結果ではなく、成長の過程にスポットを当て、これからも個性に富んだ選手たちを輩出していく。
(写真提供/SGハンドボールクラブ)