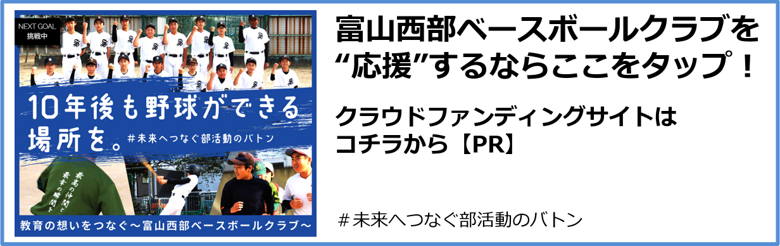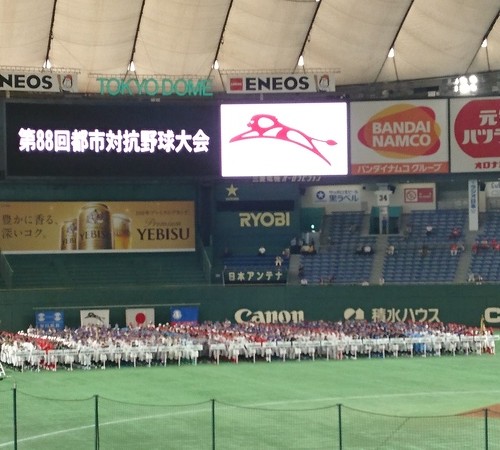「野球がしたい」中学生よ、集まれ ― 富山西部ベースボールクラブの挑戦

部活動に代わる、新たなクラブチームの誕生

2025年8月、富山県富山市内の中学校の校庭で、うだるような暑さを吹き飛ばすかのように、元気に野球の練習に励む少年たちの姿があった。呉羽中学校・芝園中学校・西部中学校の3校から集まった16人の野球少年たちである。
彼らは上記3中学校の合同野球部員ではない。新たに誕生したクラブチーム、「富山西部ベースボールクラブ」の初代メンバーたちである。
「野球部」はなくなるのか?
少子化、教員の働き方改革、そして学校外での学びや活動の多様化といった社会的背景のなかで、教育現場における部活動の在り方が、いま大きな転換点を迎えている。かつて学校教育の一環として当たり前に存在していた「部活」は、その持続がますます困難になっていくだろう。
富山市においても、2026年の夏以降は、原則として土日の部活動を中学校では実施しないという方針が打ち出されている。現状、中学野球の公式試合はほとんどが週末に組まれているので、その影響は大きい。
野球に関しては競技人口の減少が富山市のみならず全国的な問題である。以前は学校に30人、40人と野球部員がいることが普通で、校内で紅白戦だってできた。今は、ひとつの学校に野球部員が数人しかいないことも珍しくない。そうなると、試合はむろんのこと、練習すらもままならない。
活動が停滞すれば、指導者や練習時間の確保もさらに難しくなり、「野球をやりたくても続けられない」子どもたちが今後増える可能性は高い。
こうした変化に対応し、学校単位での部活動運営に代わって地域が主体となるクラブ活動が求められる。そんななか、新たな選択肢として誕生したのが「富山西部ベースボールクラブ」である。 2024年11月に設立され、2025年8月より本格的に始動したこのクラブは、「野球がしたい」という中学生の気持ちを受け止める、新しい地域密着型のクラブチームである。従来の部活動とは異なる運営体制を持ちながら、地域のスポーツ文化を次世代につなぐ取り組みを取材した。
野球人口の減少がもたらす「チームが組めない」現実

クラブ代表の岡本奎一氏は元中学校教員で、自身も選手として小学校から大学まで野球を経験した人物である。学校現場の変化と、そこに通う生徒たちの「やりたいこと」との乖離を痛感し、クラブチームの必要性を強く感じたという。
現在はかつてのように学校内でチームを維持できる時代ではなくなった。「学校の枠を超えて子どもたちが集まり、野球ができる場所」を用意することが、次の世代に野球文化を引き継ぐための鍵となる。富山西部ベースボールクラブは、まさにその課題に正面から向き合っている存在といえる。
多様な生徒が集う、開かれたチーム

3年生が夏の大会を機に活動を終え、現在クラブで活動しているのは中学1、2年生合わせて16名。(2025 年 8 月時点)。野球経験者だけでなく、初心者の生徒も歓迎しており、「野球をやってみたい」という意思があれば誰でもチームに受け入れる姿勢をとっている。
この点は、従来の部活動や競技志向のクラブチームとは大きく異なる特徴である。勝敗を第一に掲げるのではなく、スポーツとしての楽しさや達成感、仲間との連帯感などを重視。「野球が好き」「野球を始めてみたい」という気持ちそのものに寄り添う環境が整えられている。 「一度やめてしまったら戻りづらい」「下手だと恥ずかしい」という心理的な壁を取り払うことが、あらゆるスポーツ人口の維持と裾野の拡大には不可欠である。とくに野球はバットやグローブなどの道具が必要になるうえ、それらを使いこなす独特の技術が求められるので、未経験者には参加へのハードルが高いスポーツだ。そうした意味で、富山西部ベースボールクラブの「野球をやりたい子は誰でも歓迎」というスタンスは、社会的にも意義のあるアプローチといえるだろう。
柔軟な活動形態と保護者への配慮
クラブの練習は、基本的に土日と平日1回、3校いずれかのグラウンドを使用する。夏休み中は、朝7時から10時ごろまでの時間帯に集中して練習を実施しており、暑さ対策にも配慮した日程となっている。
また、運営面では、保護者への負担を可能な限り軽減する方針を採用。少年野球チームによくある「お茶当番」や「送迎係」などの制度は設けられておらず、効率的な運営体制の構築を目指している。 これは、共働き世帯の増加や、保護者の時間的・精神的な余裕の少なさを踏まえた、時代に即した運営方針といえる。保護者の負担が軽くなることで、「子どもをクラブに入れやすい」と感じる家庭も増え、結果として野球人口の裾野が広がる可能性もあるからだ。
経験豊富な指導陣が支えるクラブ運営

指導を担うのは、現職の教員2名(竹田監督・星野ヘッドコーチ)と、代表の岡本氏を含む複数名。あくまでクラブチームとして学校とは独立した組織ではあるが、学校の協力を得ながら活動していることに加え、指導員に教育経験が豊富なことも富山西部ベースボールクラブの特徴である。
教員であると同時に、所定の手続きを経て兼職兼業として地域クラブ活動に関わるという形は、今後の部活動地域移行のモデルケースにもなりうるだろう。
教育的視点と専門的な指導力を併せ持つ人材が、地域で指導にあたることは、保護者にとっても安心感のある環境づくりにつながる。
岡本氏は元選手としての豊富な経験に加え、元教員として教育現場の実情を熟知している。クラブの運営においても「選手の視点」と「指導者の視点」の両面からバランスの取れた判断を行っている。
大会出場を視野に、段階的な成長を目指す

クラブは現在、練習や基礎づくりを中心に活動しているが、今後は段階的に活動回数を増やし、日本中学校体育連盟(中体連)主催の大会などにも出場していく方針である。
公式戦への参加は、競技者としての意識を育てるとともに、目標に向かって努力する姿勢や仲間と協力する力を養う重要な機会となる。また、試合を経験することによって、技術面だけでなく、精神的な成長も促される。
クラブとしては、「結果」よりも「経験」に重点を置きながら、子どもたちの成長を支える方針を堅持していくという。競技を通じて得られるさまざまな学びが、彼らの人生にとって貴重な財産となることを見据えている。
10年後も「野球ができる町」であるために

岡本代表は、クラブの将来像について次のように語っている。
「10年後、富山に住んでいる中学生が『野球をしたい』と思ったとき、迷わず始められる環境があること。それが私たちの目指す未来です。そのために今、できることを一つひとつ積み上げていきたいと思っています」
この言葉に象徴されるように、富山西部ベースボールクラブの取り組みは、単なるスポーツ指導にとどまらない。子どもたちの健やかな成長と、地域社会の持続的な活力を生み出す土壌を育てる営みでもある。
学校、家庭、地域が連携し、それぞれの立場から子どもたちの「やりたい」に応える仕組みを作っていく。富山西部ベースボールクラブは、その一歩を確実に踏み出している。10年後のこのチームを早く見てみたい。
富山西部ベースボールクラブ公式ウェブサイト:https://sgrum.com/web/toyama-seibu-bbc/
(取材/文・角谷剛、取材/写真/協力・富山西部ベースボールクラブ)