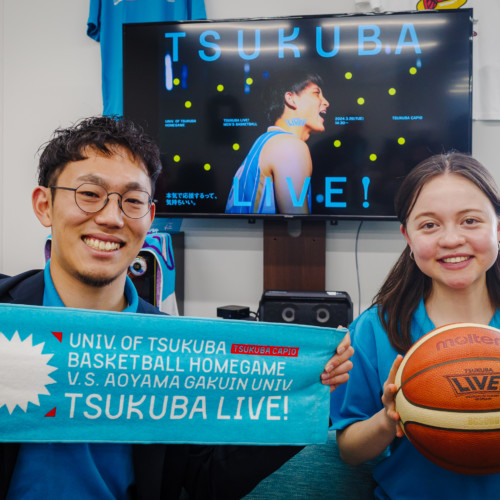10年振りの全日本大学駅伝出場を目指す名古屋大学 ~国立大学の挑戦~(後編)

三大学生駅伝の一つ、全日本大学駅伝(全日本大学駅伝対校選手権大会)。11月初旬に行われ、熱田神宮から伊勢神宮の106.8kmを8人でつなぐ。全国8地区(北海道・東北・北信越・関東・東海・関西・中四国・九州)で行われる選考会を勝ち抜いた大学と前年8位に入ったシード校で争う「真の大学日本一」を決める大会だ。箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)が人気、知名度とも最も高いが、関東地区以外の大学は出場できない。
地区によっては国立大学が出場枠を勝ち取ることも珍しくない。2021年は東北大(東北)、信州大(北信越)が伊勢路への道を勝ち取った。
東海地区では名古屋大が出場を目指している。エースであり長距離パート長(駅伝主将に相当)の森川陽之選手(4年・近大東広島)を中心にチーム作りを進め、課題だった選手層が改善されつつある。出場すれば10年振りとなる国立大学の挑戦を取材した。
学業との両立
国立大学のため学業との両立が気になるが、学部生の多くは「気にしてない」という。5000m・10000mともチーム2番目の記録を持つ重田直賢選手(3年・生野)は工学部で機械工学を学ぶ。「レポートは多いですが、時間は自分で作ればよいので、練習に支障が出ることはありません」と言う。高校時代も全国高校駅伝の都道府県予選が行われる11月まで部活動を継続していたという。
大変そうに見えるが、本人はそう感じていない。高校時代からの両立してきたこと、そして「みんなやっているから自分もできる」という相乗効果の結果だろう。
一方で大学院生(生命農学研究科)の勝田哲史選手(修士1年・広島皆実)は状況が異なる。
勝田:平日は9時から18時まで研究室にいます。夏季休暇もほとんど研究室にいました。平日もポイント練習をやっていましたが、それで体調を崩してしまいました。社会人の市民ランナーから見ると甘いのでしょうが、今は休日にポイント練習を集中して行うようにして様子を見ています。
学部や学科、学年によって状況が異なる。4年生や大学院生では配属される研究室によっても状況が異なるという。その中で自分のスタイルを見つけることが両立のポイントだ。

国立大学ならではの苦悩 全日本大学駅伝が全てなのか
一方で迷いや葛藤もある。重田選手は「12月にライバル校の選手と話して、熱量が違うと感じました」と切り出す。
重田:ほとんどの部員がスポーツ推薦で入学し、「陸上をやって当然」という覚悟があります。朝練習から本練習まで全員でやっている。「こうやったら強くなれる」という軸があるように見えます。
勝田:集合練習を増やしてもっと駅伝に特化すればもっと強くなれるかもしれません。しかし駅伝至上主義になると、選手とは大きな差がある部員を切り捨てることにもつながります。それはしたくないし、するべきではないと思います。
選手を目指す部員が高い意識を持って自立していれば個人にある程度裁量を持たせても全日本大学駅伝を目指せるし、今はそういうチームになっていると思います
全員が「目標は全日本大学駅伝出場」と言えるのが理想かもしれない。
しかし選手になれるのは8人。上位8人を目指せる部員と大きな差がある部員とでは熱量に差が出ることもある。それをどう乗り越えるかも彼らにとって大きな課題だ。
大学には全天候型の400mトラックがある。今主流のブルートラックで雨天でも練習が可能だ。一方で多くの大学が取り入れるクロスカントリーのコースが近くにない。1時間程度かけて移動しているという。
未舗装で起伏のあるコースを走るクロスカントリーは様々な効果が期待できる。
重田:故障防止のため、土の上で走れるコースが近くに欲しいです。大学近くの遊歩道は舗装されているし、芝生がある公園は人が多くて走れない。大学の野球場の裏の草を刈ってランニングコースにするという話があったので実現して欲しいです。
関係者の話では大学の許可が下りないため進まないそうだ。国立大学の敷地は国有地。許可を出せない理由も理解できるが、そうだとするとこれも国立大学ならではの制約だろう。

実り始めた新入生勧誘、OB・OGによる合宿費支援も開始
スポーツ推薦制度がなく、それも制約の一つだ。それでも新入生だけでなく、高校生の勧誘に力を入れた。高校生勧誘の強化を主導した一人である森川選手がその取り組みと成果を話してくれた。
森川:部全体で高校生の勧誘に力を入れています。進学校にはパンフレットを郵送し、勧誘専用のホームページも作りました。今はコロナ禍でできませんが、大会に行って直接声を掛けることもやっていました。
結果、短距離・フィールドではインターハイ出場者を含む実績のある部員が複数名入部して、日本インカレに出場したり、部記録を更新したりしています。男子長距離では村瀬稜治(2年・桃山)が入部してくれました。さらに2021年は5000m14分台2名、1500m3分台1名が入部してくれました。
村瀬選手は近畿大会5000m8位の実績を持つ。ライバル校の新入生とも遜色ないレベルだ。
村瀬:歴史が好きなので地元の大学で考古学を学ぶつもりでしたが、陸上競技部の活動が活発ではないことは気にしていました。勧誘パンフレットが高校に届いたので名古屋大学も調べて、考古学が学べるということで志望校を変えました。
森川:村瀬の場合、高校の先生の協力が入学につながりました。先生には本当に感謝しています。
高校の先生には村瀬選手に陸上競技でも活躍して欲しいという想いがあったのだろう。そんな想いも選手を後押しする。
資金面でも新たな取り組みが始まった。すべて自費で賄っていた合宿費の補助が出るようになった。陸上競技部のOB・OG会に要望した結果、合宿費補助に予算が付いた。これまでも支援はあったが、駅伝強化に特化した支援はなかった。OB・OGも部員の想いを後押しする。
コーチも同じルーツを持つ同士
指導する林コーチは豊橋技術科学大学出身。大学時代は東海インカレ3000m障害優勝、全日本大学駅伝には東海学連選抜で出場している。
大学院修了後の2012年から名古屋大学に技官として勤務。一緒に練習するなどの交流があった。2013年の全日本大学駅伝東海地区選考会後に前任者の金尾洋治氏(現東海学園大)から後任を頼まれコーチに就任した。
――どのような指導をしているのでしょうか?
林コーチ:集合練習はほとんど見ていますが、練習メニューは学生が作成しています。自分たちで考えたメニューの方がやりきろうとしますし、目的や意図も意識するからです。負荷が高すぎると思ったら指摘はします。練習では顔付きや筋肉の張りなどの細かい変化も見ます。そこから成長や練習不足の兆候がわかり、アドバイスすることができます。
――特に意識していることは?
林コーチ:「陸上競技を楽しむ」ことです。そのために嫌いになるような経験をさせないこと。特に失敗したときの声の掛け方に特に気を遣っています。
また競技に無関係な楽しい経験も大切なので、趣味の海釣りで釣った魚を食べてもらっています。栄養面でもプラスになりますし。最近は「魚ください」と催促されるので、私が食べる分がどんどん減っています。
自身も学ぶことを中心に大学を選び、その中で陸上競技も続けてきた。いわば「同じルーツを持つ同士」である。そんな同士らしい自主性を重視した指導だ。

混戦が予想される東海地区代表争い
全日本大学駅伝東海地区選考会は6月に開催予定。各校8名が10000mを走り、その合計タイム上位2校が全日本大学駅伝に出場できる。
皇學館大は5年連続出場。選手層が厚く一歩リードしている。続くのは昨年の選考会で2位の岐阜協立大、東海学生駅伝2位の愛知工業大。昨年3位の中京大は選手層が厚くなれば代表校争いに絡む可能性がある。客観的に見ると名古屋大の状況は厳しい。記録だけでなく勝負強さも求められる。成長を見せ、代表校争いに絡んだときは4~5校が2つの枠を争う大混戦が予想される。
皇學館大の日比監督は実業団で選手・監督を経験している。また岐阜協立大の揖斐監督も実業団を経験、高校(土岐商)、大学(駒澤大)では駅伝のスター選手だった。関東地区では主流になった実業団出身の監督が東海地区でも見られるようになってきた。
こうした大学に国立大学の名古屋大が挑む。
三大駅伝で優勝を争う関東地区の大学は10000mの平均タイムが28分台、対して東海地区代表を争う大学は30分台。
大きな差はあるが、地元で行われる全日本大学駅伝で戦いたいという想いが選手を成長させる。川瀬翔矢選手(皇學館大→ホンダ)は2020年全日本大学駅伝で2区区間賞。卒業1年目で2022年全日本実業団駅伝優勝メンバーとなった。38歳で10000m28分03秒73まで記録を伸ばした中村高洋選手(京セラ鹿児島)は名古屋大出身だ。
混戦が予想される東海地区の全日本大学駅伝代表校争い。6月の選考会、そしてそこに挑む選手の成長に注目して欲しい。
(取材協力/写真 名古屋大学陸上競技部)