リオデジャネイロ五輪銅メダリスト・小堀勇氣さん 24年間の競技生活で感じた「最後まで完成はしなかった」その真相と水泳生活のルーツ

かつて競泳日本代表として2度の五輪(2012年ロンドン・2016年リオデジャネイロ)に出場し、リオ五輪では男子800mリレーで銅メダルにも輝いた小堀勇氣さん。
昨年10月に現役生活にピリオドを打ち、現在は所属先であるミズノで水泳に関する業務を担当している。今回、小堀さんにその現役生活について振り返ってもらった。
(取材協力 :ミズノ株式会社 文:白石怜平)
原点は「過呼吸になり途中棄権」を繰り返した小学生時代
石川県能美市出身の小堀さんは、3歳から水泳を始めた。お姉さんがやっていたことがきっかけで、自身も地元の能美スイミングクラブに通い始めた。
競泳生活の原点となったのは引退表明時に寄せたコメントでも語った小学生時代。競技会に出場し始めた3年生のころ、レースで緊張しすぎて過呼吸になり、途中棄権してしまうことが続いたのだという。
「緊張しすぎて普通に(レースの途中で)何度も止まるんです。床に足をつくと失格になってしまうので、記録として残らない。そんなことが20回中20回とか本当に続いていました。
それでも、次の日練習があったら自然とプールに行っていたのです。なので、泳ぐのは好きで続けることは全く苦ではなかった。試合になるとどうしても緊張してしまいましたね」
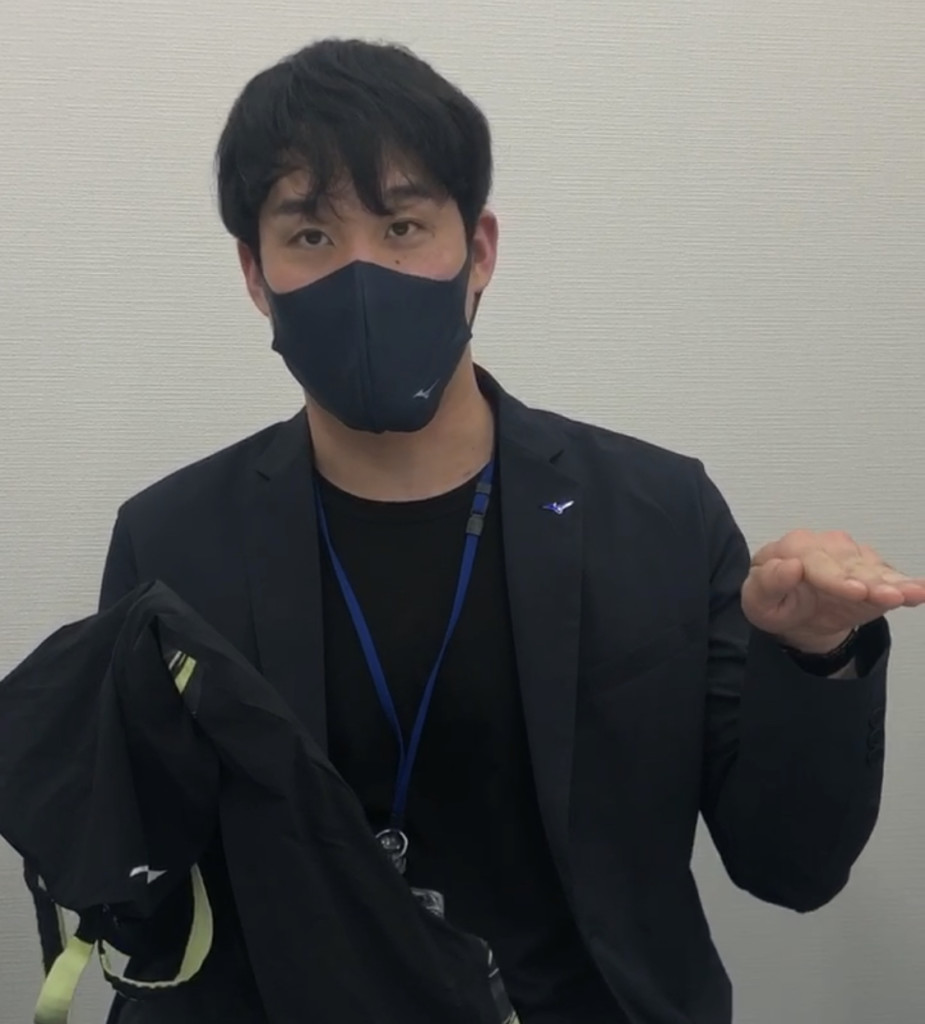
レースでは緊張してしまうものの、練習は継続していたためメキメキと上達していた。ここから克服への道が拓かれていった。
「練習でもタイムが上がっていったので、前よりも速くなっている実感が持てました。『俺できるよな』と思えてから、試合になるにつれて何とか克服したい想いが強くなりました。
そのためにとことん泳ごうと思って、『休みは要らないから練習させてほしい』と。小学校の時に365日だったら360日くらいはやっていました。それだけ克服したいという気持ちがあったので。完全に克服できたのは小学校6年生の時でした」
ジュニア記録を次々と更新 ”北陸の怪童”を襲名
中学進学後も周囲を凌駕する練習量でさらに実力を伸ばしていった。次々と中学記録を更新し、3年時の08年、世界ジュニア選手権の800mリレーでは銅メダルを獲得した。
次第にその活躍ぶりは全国に広がり、”北陸の怪童”としてその名を轟かせていく。卒業間近の09年1月に行われたジュニアパンパシフィック選手権では、200mバタフライに出場し金メダルに輝いた。
「ちょうど身長が伸びる時期が早く、体の成長に合わせてハードなトレーニングもできたので、タイムが伸びていったと思います。あとは誰よりも泳いだという自負もありました」
金沢高校2年時の10年には、中国・広州で行われた第16回アジア大会に最年少選手として選出。個人では200m自由形、リレーでは800mリレーに出場した。
以降は自由型とバタフライを得意競技とし、シニアでの日本代表に名を連ねていった。
12年ロンドン・16年リオデジャネイロと2大会連続で五輪出場
日本大学へ入学してすぐの12年夏には、ロンドン五輪日本代表にも選ばれ800mリレーに出場。誰もが憧れる世界最高峰の舞台に立った。
ここではメダル獲得とはならなかったが、ジュニア時代から国際大会など大舞台での経験を多く重ねてきた小堀さんにとっては、大きな緊張もなく臨めたという。悔しさの中に、次のリオデジャネイロへと目標がすぐに切り替わる出来事があった。
「すごく覚えてる言葉がありまして、ロンドン五輪の400mメドレーリレーで日本が銀メダルを獲得したのですが、メンバーの1人が尊敬する先輩の藤井拓郎さんでした。
表彰式後にメダルを僕のところに持ってきてくれて、首から下げていて『あぁ肩凝るわ〜メダル重いぞ〜』って言っていたんです。あの言葉がずっと残っていて、『次、自分も獲りたいな』って思った瞬間でした」
リオデジャネイロまでの4年間、小堀はその実力にさらに磨きをかけていく。13年の200mバタフライで日本選手権初優勝を飾ると、翌14年のアジア大会では800mリレーで金メダルを獲得。名実ともに日本を代表する選手へと駆け上がっていた。

16年4月、大学を卒業し現在も所属するミズノに入社。そして4年前から目指していたリオデジャネイロ五輪代表へ順当に選ばれた。
「ロンドンに降り立った時、会場の至るところにかかっていたオリンピックの装飾を見て、『オリンピックってすごいな』と少し興奮していたのですが、リオの時はロンドンの経験を踏まえて戦えたというのがすごく大きかったです。世界水泳や日本選手権とあまり変わらず平常心で挑めました」
小堀さんは前回同様、800mリレーに出場した。松田丈志選手・萩野公介選手・江原騎士選手という錚々たるメンバーと共に臨み、その力をいかん無く発揮。64年の東京五輪以来52年ぶりとなる銅メダルの獲得に大きく貢献した。
「一緒に泳いだ3人すごい先輩と後輩、同級生がメンバーで『本気でメダルを獲りに来た』という気持ちで試合に臨むことができました」
コロナ禍で一度は引退も考えるも、東京五輪に照準を
リオデジャネイロでメダルを獲得し、次は母国の開催となる東京五輪でのメダルも自然と期待が高まっていく。
18年、日本チームはパンパシフィック水泳選手権では400mリレーで銀・800mリレーで銅、同年ジャカルタで行われたアジア大会では800mリレーで金に輝くなど、その期待に違わぬ活躍を続けていた。
しかし、20年から状況が一変した。世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルスである。同年に開催が予定されていた五輪も1年延期。自粛ムードが高まり、街から人が消えていった。
小堀さんは当時の状況を語った。
「うーん…まずは競技をどうしようかなと。1年は相当長いですし、4年に1度に向けて身体・気持ちをつくり上げていった中で、もう1年目標に向かっていけるのかを確認したいと思いました。
ただ、実際はすごく迷っていて、延期になってから1ヶ月ほどお休みをいただいき考えていました」
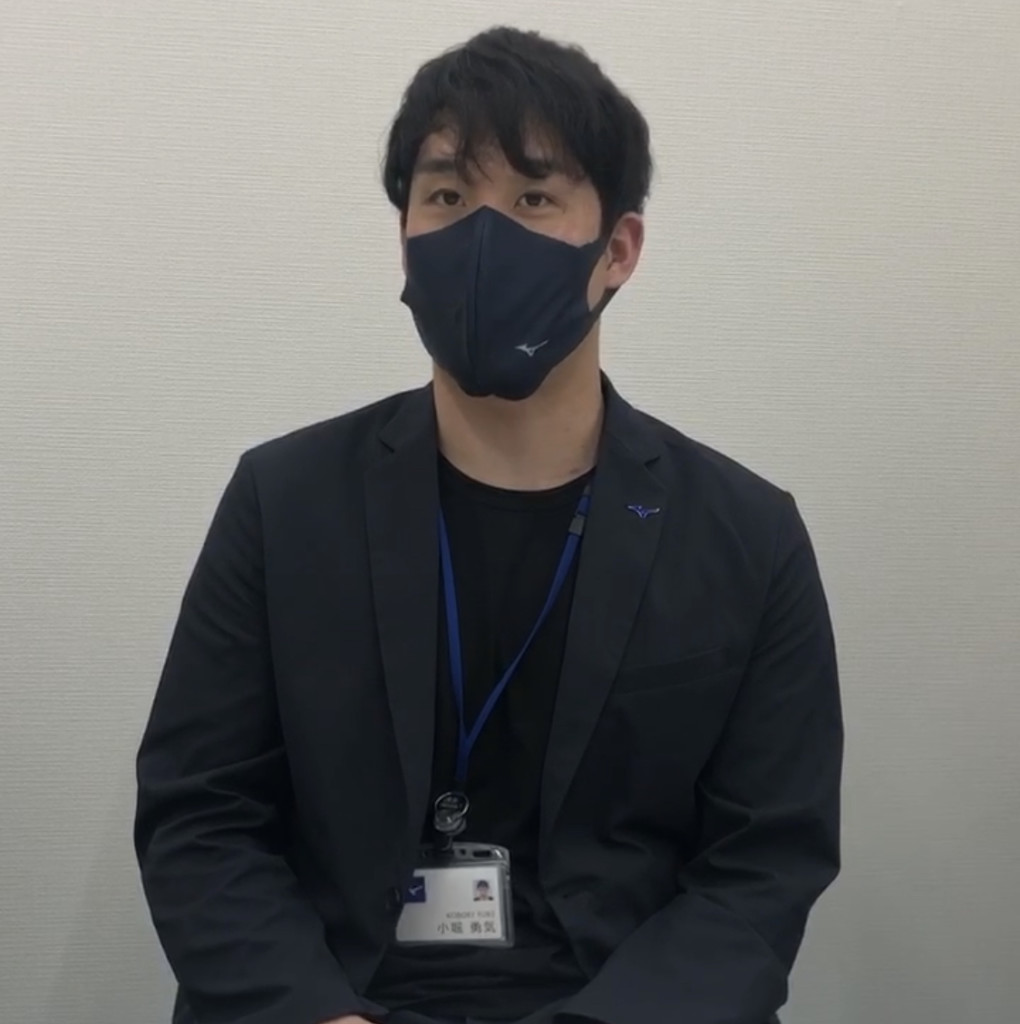
選手生命は短く限りのあるアスリートにとって1年という期間は競技人生を左右する。心の底では引退の方に気持ちが動きつつあった。
「もう辞めようと思っていたら、担当の平井伯昌先生が『プールに行って来い』と。『まだ泳ぐかどうかも決めてないので行かないです』と言ったら、『いやプール行って来い』と無理矢理(笑)。
自粛期間中だったので内緒で僕をプールで泳がせてくれたんです。泳いだら『やっぱり泳ぎたいな』と自然に思えたんです。泳いでみたらその迷いが吹っ切れました」
迷いがなくなった小堀さんはトレーニングを再開。施設は閉鎖していたため、大学からエアロバイクを自宅に運んで漕いだり、床にマットを敷いて筋力トレーニングを行うなど、限られた中でできることをこなしていった。
しかし、1年の期間というのは小堀さんの歯車を狂わせ、そして元に戻ることはなかった。最終選考会で結果を残せず落選となってしまった。
「最終選考会で結果が出なくて1ヵ月ぐらい引きずっていました。ただ、シンプルに競泳というスポーツは速く泳げる選手が代表になれるので、この時に速い選手・強い選手が日本代表として出場する。
なので当然の結果だと。そう考えられてからは、大会で”ジャパンを応援したい”と純粋に思いながらTVで観戦していました」
「タイムはまだ伸びる」そう感じた中での決断
そしてこの年の10月、24年間続けた競技生活にピリオドを打つことを決断した。その決め手は何だったのか。
「トータルです。ただ、タイムとしては伸びるかもしれない。むしろタイムを伸ばせる自信は実はありました。21年の4月で代表落ちしてから夏に1つ大会に出たのですが、今までと自分が無我夢中で泳いできた部分と、以前から構築してきたの水泳の理論、
”ここを使えば身体をうまく使える”といったことが体現できるにようになったのが、昨年の4月から8月位までの間でした。なのでこのままいけばもっとタイムを伸ばせるだろうと思っていたんです」
タイムを伸ばせる自信がありながらも、なぜ引退を決めたのか。
「タイムを伸ばすことが、今後の人生にとって必要かと言われるとそれは違うと感じたんです。社会人として働くキャリアというのも考えました。あとは肩を長く怪我していたので、それも考えたときに、トータルで考えて辞めるべき時なのかなと」

先々の人生も考え、最終的に決断したのは9月中旬、10月に正式に引退表明をした。
3歳から水泳を始めて競技としては24年間プレー。五輪に出場しメダルも獲得するなど輝かしい実績を残した。しかし、それでも意外な言葉が出てきた。
「悔いは今でもありますし、考えるとすごくたくさん出てきます。泳げばもうちょっとタイムが伸ばせると感じていた中でしたから。
それを線引きするというのはすごく苦しかったし、水泳しかやってなくてそれがピタッと止まったときに、自分がどう生きていけばいいのかという不安もありました。今でも仕事でプールに行くと”泳ぎたいな”と思う時もあります」
”まだ伸びる”・”これからどう生きていくのか”
そんな思いや状況が絡む複雑な状況の中で下した決断。最後に現役生活とは何であったかを改めて振り返ってもらった。
「完成しなかったと思います。例えていうとダルマの最後に目が入っていない状態です。でもそれがいいのかもしれないです。ただ、この2年間感じたのは、インターハイとか全国大会がなくなってしまった方たちがたくさんいらっしゃいます。
自分の意志などとは関係なく目の前から消えてしまった訳ですよね。それを見ると心が痛いですし、むしろ僕は自分で決断できた訳ですから、幸せなことなのだと思います」
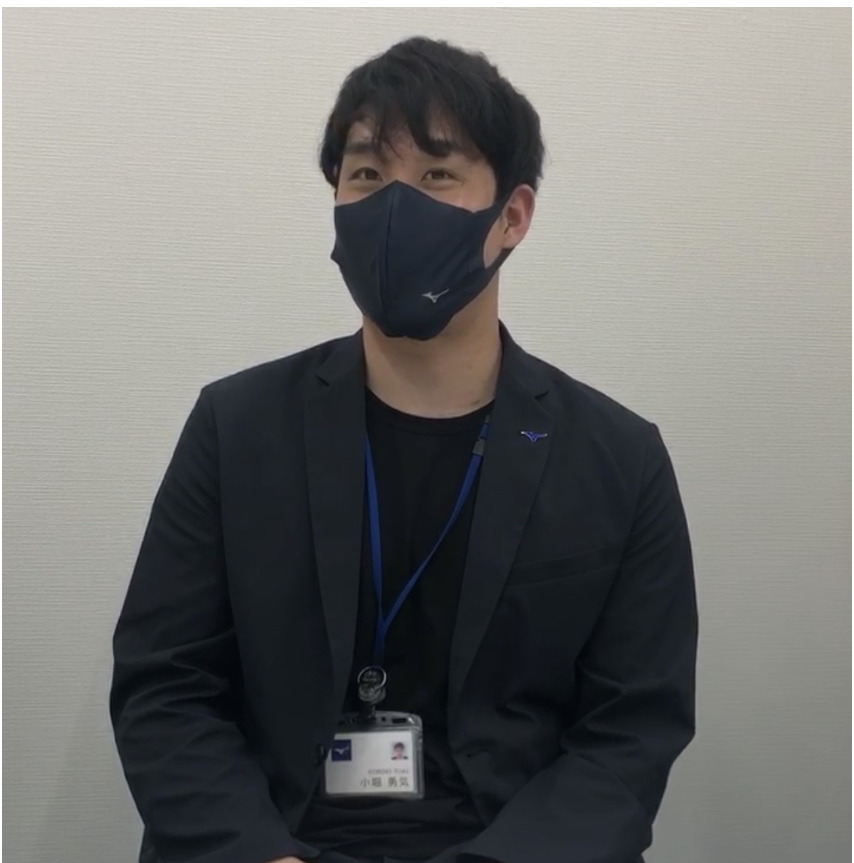
現在は、ミズノのコンペティションスポーツ事業部のマーケティング部に所属し、水泳担当として全国を回っている。行った先々でコーチや生徒から質問や講演の依頼を受けるなど、知名度と実績を活かし新たなフィールドでも輝きを放っている。
「今は今でやるべきことがたくさんあります。任せていただいていることもたくさんあります」
胸を張って第二の人生に真剣に向き合うその表情は勝負師の顔そのものだった。片目が塗られていないそのダルマは、小堀さんの挑戦の証でもあった。










