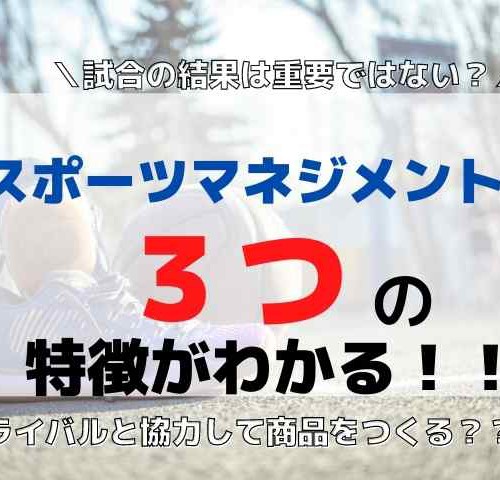高校野球の「投球過多」にまつわる取り組みは、どう変化してきたか?

広尾晃のBaseball Diversity
高校野球の前身である中等学校野球大会がスタートしたのは今から110年前のことだ。1924年には、甲子園球場もでき、中等学校野球は、全国的な人気を博するようになった。
それから1世紀、春、夏の高校野球全国大会(甲子園)は今も国民的な人気スポーツだが、同時に多くの問題が起こった。とくに「投球過多」に関わる問題は、近年大きな課題になっている。
延長戦をめぐるルール変更
もともと中等学校野球の時代には、高校野球は延長戦は決着がつくまで試合をすることになっていた。1933年夏の甲子園、準決勝の明石中―中京商は、大会史上最長の延長25回までとなり中京商が1-0で勝っている。
1958年、春季四国大会で、徳島商の板東英二が高知商との延長戦16回を一人で投げ抜いた翌日、高松商との延長戦25回を一人で投げ抜き、大きな話題となったが、これを問題視した日本高野連は大会規定を急遽変更し、延長18回で勝敗が決まらないときは「引き分け再試合」とすると決めた。
投手の「投球過多」について、高校野球が制限を設けたのは、これが最初だった。
延長戦の規定は、2000年には15回までとなり、さらに2018年から延長13回以降は「タイブレーク」となり、2023年からは延長10回以降「タイブレーク」となっている。

夏の甲子園決勝での疲労骨折
1991年夏の甲子園、沖縄水産は決勝戦まで進出したが、エースの大野倫は、大会前からひじ痛に苦しみ、痛み止めの注射を打ってマウンドに上がった。
大阪桐蔭との決勝戦では打ち込まれて敗退。大野は夏の大会を1人で投げ切り、球数は773球に上ったが、閉会式での大野の右腕は不自然な方向に曲がっていた。沖縄に帰ってから、右ひじの剥離骨折が明らかになった。大野倫はのち野手として巨人に入団するが、投手は断念せざるを得なくなった。
当時の日本高野連会長の牧野直隆はこれを深刻に受け止め、甲子園大会前に出場校投手の肩ひじの「メディカルチェック」を導入することを決定。試行期間を経て1994年から、春夏の甲子園に出場が決まった選手は、整形外科医などによるメディカルチェックを受けることとなった。
またこの年の春の甲子園から投手数の増加に対応するため、ベンチ入り人数は15人から16人に増えた。

大エースが投げまくる時代に
1990年代から、甲子園で活躍する大エースが大きな話題になった。これら投手は一人で多くの球数を投げた。
横浜高の松坂大輔は1998年夏の甲子園を一人で投げ抜き、決勝戦でノーヒットノーランを記録したが、球数は767球に上った。
2005年の夏、早稲田実業の斎藤佑樹は、決勝戦の延長引き分け再試合も含めて948球を投げた。決勝戦の相手の駒大苫小牧の田中将大は、もう一人の投手とともに投げたが、それでもこの大会の球数は658球に上った。
こうした投手も、甲子園大会の前には整形外科医などのメディカルチェックを受けてはいたが、ドクターストップはかからなかった。医師は「2週間の大会を投げ切るために支障があるかどうか」を判断したが「投球過多」の将来への影響は考慮しなかった。

アメリカが指摘した「投手の酷使」
こうした状況に変化があったのは、2013年春の甲子園で準優勝した愛媛県済美高の安樂智大が決勝まで772球を投げた時だった。
アメリカのジャーナリスト、ジェフ・パッサンが安樂や済美高上甲正典監督を取材し、アメリカのメディアに「日本の高校生投手は酷使されている」という記事を書き、大きな話題となった。パッサンは「THE ARM(邦題:豪腕 使い捨てされる15億ドルの商品)」という著書を書いたが、これが日米でベストセラーとなり「投球過多」「登板過多」の問題が、日本でも注目されるようになった。
「有識者会議」の答申
2018年、夏の甲子園で金足農、吉田輝星が初戦から決勝戦の途中までを投げ抜いた。球数は2005年夏の斎藤佑樹に次ぐ881球に上った。決勝戦の相手の大阪桐蔭が、根尾昂、柿木蓮・横川凱と3人の投手を起用していたこともあり「高校野球でも球数制限をすべきではないか」という声が上がり、日本高野連は翌2019年、高校野球指導者、整形外科医、弁護士などからなる「投手の障害予防に関する有識者会議」を設置し「球数制限」など投手の健康問題について議論した。
有識者会議は、この年の11月20日に日本高野連に答申を提出。
その答申を受けて「大会期間中に1人の投手が投げる総数を『1週間500球以内』とし、3連戦を避ける日程を設定すること」という「球数制限」が、翌年春の甲子園から導入されることになった。
この「球数制限」は、2003年に日本臨床スポーツ医学会学術委員会、整形外科専門部会が発表した「青少年の野球障害に対する提言」が目安となっている。

「球数制限」をめぐる賛否両論
2019年の答申には、多くの賛否両論があった。
まず、旧来の「高校野球の伝統」を重んじる指導者、関係者からは
「一人のエースがチームをけん引して大会を投げ抜く高校野球の良さが失われる」
という意見があった。
また、高校野球の「公平性」を考える指導者からは
「2人、3人と投手をそろえることができる私学はいいが、1人のエースが投げるしかない公立高校などと、戦力格差が広がる」
という意見もあった。
一方で「1週間500球以内」という規定そのものが「緩すぎる」「実質的な投げ放題だ」という正反対の批判もあった。
アメリカでは、18歳以下の野球選手の1試合当たりの投球数、登板間隔について定めた「ピッチスマート」を2014年に導入した。これによれば高校生に相当する17~18歳は、1日の球数の上限は105球。31-45球を投げた場合は中1日の休養が必要で、76球を超えると最低でも中4日、休養しなければならない。
この規定に比べれば、日本の高校野球の「球数制限」は「あってなきがごとし」だということだった。
大きく変化した「投手起用」
賛否両論がある中で、翌2020年春の甲子園から「球数制限」が導入された。
この年は新型コロナ禍によって高校野球も活動を制限されたが、2021年以降の高校野球の動向を見ると、各校の投手起用は予想以上に大きく変化している。
夏の甲子園で言えば、「1週間500球以内」をオーバーする学校は出ていない。1大会で1人で500球以上投げた投手は、2022年近江高の山田陽翔の644球と、聖光学院の佐山未来の551球の2人だけ。
23年夏優勝の慶應義塾高は、小宅雅己(362球)鈴木佳門(185球)松井喜一(91球)と3人の投手を起用。24年夏優勝の京都国際高も中崎琉生(441球)、西村一毅(339球)と2投手を起用した。
多くの高校では、2人以上の投手を先発、救援で起用したり、ローテーションで投手を起用するなど「投手の分業化」が進んだのだ。
指導者の世代交代が進み、精神論ではなく、科学的な知見も取り入れた指導者も増えたことが大きいと思われる。
日本高野連の「球数制限」は、高校野球指導者の「意識変革」につながったという見方ができるだろう。

さらなる問題も
しかし近年、高校野球は次の課題に直面している。弾道計測器「ラプソード」など、投球メカニズムを精緻に計測することができる機器の導入、バイオメカニクス(生体工学)の進展などによって、投手の投球強度(球速)が、急速に高まっている。
このために、球数は少なくてもじん帯を損傷するなど、投手は新たなリスクにさらされつつある。すでにアメリカでは研究者がこうした報告をしているが、高校野球はさらなる対策が必要になってくるだろう。