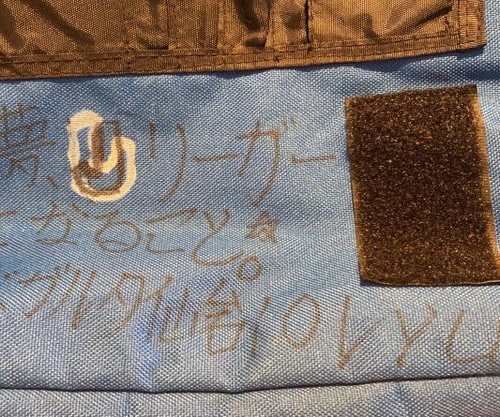横浜FCがつくる未来―マルチクラブオーナーシップとUDオリヴェイレンセ―

横浜FCを保有するONODERA GROUPは、2022年11月、ポルトガルリーグ2部に所属するUDオリヴェイレンセ(以下、オリヴェイレンセと省略)の経営権を取得した。このことは横浜FCはマルチクラブオーナーシップ(以下、MCOと省略)というクラブ戦略の下で、日本の資本でヨーロッパの市場に直通ルートを持つことができるようになったことを意味している。
近年、海外のサッカーチームの情報は日本でも手に入れることができるようになった。しかし、ポルトガルの、特に2部リーグのクラブについては、いまだに情報は多くない。おそらく日本ではオリヴェイレンセというチームについて「日本の横浜FCと深い関連があることは知っているが、どんなチームなのかはよく知らない」という人が多いのが実情ではないだろうか。
今回、株式会社横浜フリエスポーツクラブ(横浜FC)MCO事業本部の松本雄一氏と、横浜FCアカデミーダイレクターの菊池彰人氏に、マルチクラブオーナーシップとオリヴェイレンセというチーム、そして選手育成などについて、話を聞くことができた。
※取材実施は2025年6月

ポルトガルのチームがもつアドバンテージ
最初に、今回のONODERA GROUPによる横浜FCとポルトガルのUDオリヴェイレンセとのマルチクラブオーナーシップの目的を教えてください。
松本雄一氏(以下、敬称略)「まず、日本側の視点での大きな目的としては、昨年のパリオリンピックでも活躍した横浜FCアカデミー出身の斉藤光毅選手(クイーンズ・パーク・レンジャーズ・フットボール・クラブ所属)のような世界のクラブで活躍できる選手を再現性をもって輩出したいということがあります。
そのため、今回のMCOには、3つの主な目的をもたせています。第1の目的は、日本側のオーナーシップで選手のヨーロッパ市場へのアプローチを可能にして、そこで選手の市場価値を上げることです。MCOにより、選手は18歳になってすぐにでも国際移籍をして、オリヴェイレンセで欧州の市場に挑戦できるようになりました。ポルトガルでのプレーを通じて、ヨーロッパのサッカー市場にまず乗ることができますし、そこで試合経験を積んで価値を高めることができ、かつ各国のサッカー関係者の目にとまる機会をより多く作ることができます。
第2の目的は、若手選手の海外挑戦を後押しし、成功の確率を高めることです。その結果として、横浜FCのアカデミーのブランディングやリクルーティングにも寄与すると考えています。あるアンケートで横浜FCアカデミーの選手に将来の目標を尋ねると、8割を超える選手が『海外でプレーできるような選手になりたい』と回答しました。ですから、今回のMCOを通じて、選手が海外へ挑戦する実績を作ることで、より多くの可能性のある選手が横浜FCを目指すようになってほしいと思っています。
3つ目の目的は、選手が移籍する際に発生する移籍金を含めた強化費の効率化です。今、世界中でサッカー選手の移籍金が高騰しています。例えば、外国籍の選手を一人獲得するときに移籍金+年俸で非常に高額な契約になり、シーズンが始まってみたら、その選手が日本のリーグにフィットせず期待したパフォーマンスを発揮できないというリスクは常に付きまとうと思います。
現在横浜FCにはジョアン・パウロという、オリヴェイレンセから移籍してきた選手がいます。彼の場合、オリヴェイレンセでの彼のプレーの特徴、パーソナリティを把握したうえで、『この選手なら、日本のリーグでもマッチするだろう』と判断して、契約することができたと聞いています。そのため、前述のようなミスマッチのリスクは低いものになりましたし、総合的に見て選手獲得の投資効率は向上していると思います。」

今回のMCOの相手として、オリヴェイレンセを選んだ理由は、どのようなものなのでしょうか。
松本「まず、オリヴェイレンセが世界でもトップレベルのリーグがあるポルトガルのチームであるということがあります。ポルトガルリーグはUEFAランク7位のハイレベルなリーグなので、そうした環境で戦うことは、選手の成長と市場価値を上げることが期待できます。
例えば、海外で選手がプレーするときには常に就労ビザの問題が付きまといますが、ポルトガルはプロサッカー選手としての就労ビザを取るためのハードルがヨーロッパ諸国の中でも比較的低い国になります。その意味で、就労ビザがとりやすい国です。
また、オリヴェイレンセのあるオリヴェイラ・デ・アゼメイスを含めポルトガルは治安もよく、物価も安い国なので、若い選手が暮らしやすいという環境のメリットもありました。
また、オリヴェイレンセはポルトガル第2の都市であるポルトからも近く、スペインからも非常に近い街です。ヨーロッパの他国からのアクセスが良いので、ヨーロッパのサッカー関係者も足を運びやすく目にとまりやすいであろう、ということも理由の一つです。」
ちなみに、横浜FCはオリヴェイレンセというクラブをどのような特徴があるクラブだと認識されているのでしょうか。
松本「所属選手たちはステップアップを目指して非常にハングリー精神が旺盛です。また、クラブとしてはサッカー以外にもバスケットボールやホッケーなど多様なスポーツチームが存在し総合型スポーツクラブとして地域にとても根差しているクラブです。ただ、前述のように、ポルトガルリーグは非常にレベルが高いのですが、一部のビッグクラブ以外は経営難に苦しんでいるクラブが多いのも実情です。オリヴェイレンセも2019年に日本の資本が入って、クラブも老朽化したスタジアムの改修や設備投資ができるようになり、今回のMCOの基礎を作ることになりました。」
今後MCOを他の国や他のクラブに拡大していく予定はありますか。
松本「今の時点では現状のMCOのプラットホームをいかにうまく活用して、選手をヨーロッパ市場に送り出し、いかに成長させていくのかを重視していくことになると思います。」

自律の精神と自分の優位性を磨くこと
菊池さんに伺います。横浜FCの育成哲学とは、一口に表現するとどのようなものでしょうか。そして、その育成哲学は、オリヴェイレンセの育成哲学と何らかの共通点があったのでしょうか。
菊池彰人氏(以下、敬称略)「横浜FCの育成哲学を一言で表現するなら、『主導権を握って、攻撃的にプレーをする』ということになり、選手はピッチの内外で自主性や主体性を持って生活することが求められます。そして大人たちは学生生活・家庭生活・クラブの3つの場面で互いに連携を取りながら、選手が主体的に日々の生活を送れるように、選手をケアすることになります。
こうした横浜FCの育成哲学はオリヴェイレンセの育成哲学に共通するものというより、オリヴェイレンセのような海外のクラブへ行っても、日本と同じように活躍するための選手のメンタリティの基礎になるものだと思います。
オリヴェイレンセはまだビッククラブではなく、選手側にハングリーな気持ちが必要なクラブです。そうした状況で、自分で考えて、日本とは違う環境にもまれながら、サッカー選手としての評価を獲得していかなくてはなりません。そのため、自分から動いて状況を変えることができる力は、ピッチの中はもちろん外でも必要になります。」
すでに横浜FCアカデミーから永田滉太朗選手と高橋友矢選手の2人が、オリヴェイレンセでプレーしています。2選手が最初にオリヴェイレンセでプレーし始めたとき、どのようなことを話していたか覚えていらっしゃいますか。
菊池「2人とも、最初にグラウンドの質の違いを話していました。ヨーロッパ式のぬめっとしたグラウンドのコンディションが日本とは大きく異なっていたそうです。また、比較的小さなクラブということもあり、トレーナーやマネージャーの数も多くはないので、そうした選手へのサポート体制の日本との違いについても話していました。
また、食事を含めて、コンディションを整えるのも慣れるまでは大変だったようです。2人とも若いこともあり、特に永田はあっという間に現地に適応したように見えたのですが、やはり腹痛などに苦しんだこともありました。
チームメイトは国際色豊かで、特にブラジル人の選手が多く、英語とポルトガル語がメインの言語になるのですが、今では2人とも『ポルトガル語を話されても、相手が何を言っているのかなんとなくわかるようになった』と言っています。
いろいろ大変なこともあったのでしょうが、2人とも『逃げ出したい』とは一度も言いませんでした。その点は横浜FCで培った自律の精神が、ポルトガルで発揮されているのでしょうね。」
松本「永田が最初にオリヴェイレンセに行ったときには、1週間でなんとなく現地の生活に適応できたように思えたのですが、その年の年末にポルトガルで体調を崩し、その状態が長く続いて、現地の病院へ駆け込んだこともありました。とはいえ、海外では、日本にいる時と同じように病院に行けるわけではないので、そのあたりはかなり大変なようでした。
しかし、そうした困難も乗り越え新しい環境にも適応して、2年目ではレギュラーに定着しコンスタントに試合にも出場できたので、横浜FCアカデミーの取り組みが実を結んだのかなと思っています。」
永田選手と高橋選手は、どのような経緯でオリヴェイレンセへの移籍することになったのでしょうか。
菊池「2人とも横浜FCのトップチームでプレーをするレベルの選手になったときに、オリヴェイレンセへ行くことになりました。
2023年の永田の移籍時には、彼が18歳になった直後に、クラブはトップチームへの昇格と、オリヴェイレンセへの挑戦の2つの選択肢を提示しました。そうしたら、彼は迷わず後者を選択しました。もともと永田が海外のチームでプレーしたいという強い希望を持っていることは私たちも知っていたので、当然の選択だと思いましたし、彼は自分に非常に厳しい選手なので、オリヴェイレンセでもやっていけると考えて、送り出すことにしました。
その後、高橋がオリヴェイレンセへ行くことになりますが、彼ももともと海外でプレーしたいという気持ちが強かったですし、やはり自分に厳しく向き合えるタイプの選手でした。そして、永田がオリヴェイレンセに行った3か月後ぐらいから、『自分もオリヴェイレンセでプレーしたい』と意思表示をしていたんです。だから、永田の背中を追う形でオリヴェイレンセへ移籍したという感じですね。」

先日菊池さんは横浜FCのU-14と一緒に、スペインとポルトガルに遠征に来られていたと伺いました。日本とポルトガル、スペインのU-14世代の選手の違いというものは、何か感じられましたか。
菊池「スペインではラージョ・バジェカーノとアトレティコ・マドリードのU-14と、そしてポルトガルではスポルティング・ブラガのU-14と試合をしました。スペインは両チームとも選手の技術が高く、戦術をよく理解している選手ばかりで、非常に良いチームでした。
スポルティング・ブラガのU-14は、選手個人のフィジカルが圧倒的に優れていて、私たちはコテンパンにやられてしまいましたね。
試合の結果だけを見ると、例えば5-0のようなスコアで大きく私たちが負けてしまった形ですが、選手たちが若いうちにトップレベルとの差を体感できたことは非常に大きなプラスだったと思います。」
フィジカルの違いのお話がありましたが、スペインのサッカーファンに日本選手の印象を聞くと、「体が小さい」と言われてしまうことが多いんです。おそらく、オリヴェイレンセで活躍している永田選手と高橋選手もそうしたことを日々感じながら、プレーしていると思うのですが。
松本「特に永田は160㎝もない小柄な選手なので、言葉に出したことはありませんが、オリヴェイレンセでプレーし始めたころは、苦労したのではないかと思います。でも、彼も高橋も足元の技術は本当に素晴らしいものを持っているので、そうした自分の優位性を生かして、体のハンディを乗り越えています。特に永田はガッツもあり、日頃から『背の小さい人たちの希望になりたい』と言っている選手です。彼がオリヴェイレンセでプレーした当初は、パスを受けても相手チームの選手にボールを奪われてしまう場面が見られたのですが、本人曰くトラップの角度を変えるなど工夫した結果、今はほとんどボールを取られることもなくなり、以前にも増してボールが集まってくるようになりましたし、今シーズン3ゴールを決め結果も残しました。
永田も高橋も『横浜FCユースの選手のレベルはポルトガルの同世代と比べて決して低くはない』と話しています。だから、自分が得意なことを生かす方法を考えて実行できれば、身体的なハンデを乗り切る方法が見つかるのだと思います。」
最後の質問になります。海外のチームでプレーする選手になるために、どのようなことが必要になるのでしょうか。
菊池「海外のチームへ行くと、日本人選手は『守られていない環境』に24時間身を置くことになります。そこにはもちろん競争がありますし、一見すると遠回りにみえるような状況を経験することになるかもしれません。そんなときに周囲の人や環境のせいにするのは、ある意味においては、一番簡単で楽な解決法なんですね。
でも、どんな状況でも、どんな小さなことであっても、自分ができることを探して実行していくという気持ちが、海外でプレーするには最も必要になるように思います。」
松本「まず、コミュニケーション能力ですね。特に言葉の壁は大きいので、横浜FCのアカデミーの選手はオンラインで英会話のクラスを受けられるようになっています。また、ポルトガルで挑戦している選手を見ていて栄養学というか、どのようなものを、どんな風に調理して食べればよいのか、ということを知っておくことも、海外でプレーしたい選手には必要になると思いました。そうした意味でも、日本にいる時から自律した生活をすることが、海外でプレーするため必要条件だと思います。」

自律すること、そしてどんな状況でも、自分のできることを探すこと、この2つの重要性を繰り返し松本氏と菊池氏は話した。もちろん、この2つは選手が何度も試行錯誤を繰り返すことで得られる能力であることも、今回話した2人は理解している。そして、そのような場に横浜FCがなろうとしている最中である。
MCOを活用して、オリヴェイレンセへ、そして世界へ挑戦する選手の姿は、近い将来に数多く見られるようになることだろう。
(写真提供 横浜FC・UDオリヴェイレンセ)
(インタビュー・文 對馬由佳理)