「打率」「打点」から「OPS」へ、価値観が変動しつつある野球記録

広尾晃のBaseball Diversity
野球は「記録のスポーツ」と言われる。19世紀半ばに東海岸で盛んになった野球は、当初から多くのチームが各地で「試合興行」を行う球技だった。
「記録のスポーツ」になったわけ
対戦相手、選手も多く、多くの試合を各地で同時に行うスポーツでは、それらを比較する「数字」が必要だったのだ。
競技者が一つのフィールドに集まって優劣を競う陸上競技や、テニス、卓球などの競技でも「数字」は必要だが、これらの競技では「勝敗」「出された記録」などをそのまま比較することになる。
しかし「リーグ戦」が基本だった野球では、異なる球場で異なる対戦相手が対戦した勝敗を比較する必要があった。さらに、最低でも18人の選手が出場するので、個々の選手の優劣も比較する必要があった。
こうした必要性から、野球には他のスポーツよりも詳細な「記録」がつけられるようになった。
「野球記録の父」と言われるのが、イギリス出身のジャーナリストヘンリー・チャドウィック(1824~1908)だった。
チャドウィックが最初に考案したのは「打率=Batting Avarege安打数÷打数」だったとされる。その後「防御率Earnd Run Averege自責点÷投球回数×9」など様々な「記録=Stats」が考案された。
以来150年、野球の世界では様々な「記録」が考案され、チームや選手の評価基準にされてきた。
近年は「データ野球」が進展し、野球の戦術や戦略も変化している。それとともに「野球記録の価値」も大きく変動している。
ここでは「打撃記録」に焦点を当てて、その意味するところと「現在の価値」について考えよう。

主要な打撃記録
オーソドックスな打撃記録は以下のようになる
試合(game):打者、走者、投手、野手として試合に出場した数
打席(plate appearance):バッターボックスに立った回数
打数(at bat):打席から四死球、犠打、犠飛、妨害出塁を除いた数
得点(run):打者、走者として本塁に帰ること(ホームベースを踏むこと)
安打(hit):打球がフェアとなり野手に捕られることなく出塁すること(一塁打、二塁打、三塁打、本塁打を含む)。
二塁打(double):打球がフェアとなり野手に捕られることなく二塁に到達すること
三塁打(triple):打球がフェアとなり野手に捕られることなく三塁に到達すること
本塁打(home run=HR):打球がフェアとなり地面に落ちる前に球場外に出ること。打者は得点を許される。またフェアの打球が野手にとられることなく本塁に帰った場合も本塁打とする(Inside The Park Homerun、日本ではランニング本塁打)
塁打(total beses=TB):安打によって踏んだベースの数
打点( run batted in=RBI):打者の安打や犠打、犠飛などで走者が本塁を踏んだ数。打点は打者に付与される
盗塁(stolen base=SB):走者がアウトになることなく次の塁に進むこと
盗塁死(刺)(caught stealing=CS):盗塁を試みた走者がアウトになること
四球(base on balls =BB):投手が打者に対しボールを4球投げ出塁を許すこと
故意四球(敬遠)(intentional base on balls =IBB):投手が打者に意図的にボールを4球投げ出塁を許すこと※故意四球は四球に含まれる
死球(hit by pitch=HB):投手の投げたボールが打者に当たること。打者には一塁が与えられる※四球と死球を併せて四死球と呼ばれる
犠打(sacrifice hit=SC):打者がバントを行いアウトになって塁上にいる走者を進塁させること。犠打が打者に付与される
犠飛(Sacrifice fly= SF):無死または一死で走者がいる際に、打者が外野に飛球を打ち、外野手や外野の守備位置にいる内野手が捕球後、走者が本塁に達すること。犠飛が打者に付与される
三振(strikeout=SO,K):打者が投手からストライクを3つ取られること
打率(batting Average=BA,AVG):安打数÷打数
長打率(Slugging percentage=SLG):塁打数÷打数
出塁率(on-base percentage =OBP):(安打数+四死球)÷(打数+四死球+犠飛)
プロ野球の一般的な「打撃個人成績」は、上記の項目を紹介している。NPBの公式サイトの個人打撃成績も、これらの項目についての数字が並んでいる。

価値観が変化する打撃記録
従来、これらの数字の中で最も重要視されたのは本塁打、打点、打率の3項目だ。この3つは「主要打撃タイトル」と呼ばれこの3つを1シーズンで獲得した打者を「三冠王」と呼ぶ。
これに次いで、NPBの打撃タイトルになっている部門は、盗塁、出塁率になっている。
今世紀に入って、統計学に基づく野球の新しい指標、セイバーメトリクスがMLB球団に導入されて以降、MLBではこれらの指標を再検討する動きが顕著になっている。
打撃三冠の中では、打率と打点の評価が急落している。
ボロス・マクラッケンという研究者が投手の「被打率=安打を打たれた率」を長期的に調べたところ、短期的に見ればその数字にはばらつきがあるか、数シーズンにわたる数字を見ていくと、ほとんどの投手の被打率が「リーグ打率」の付近に集まることに気が付いた。
そこで「安打」は、野手がたまたまいないところに打球が落ちることであり「運に左右される要素が強いリザルトだ」と結論付けた。
衝撃的な発表だったが、セイバーメトリクスの創始者であるビル・ジェームズなど専門家が追調査をしても、マクラッケンの説を覆すことはできなかった。
このことから「打率」は「打者の能力を示す重要な指標ではない」ということになった。
また「打点」は、本塁打を打っても走者の有無によって1~4点とばらつきがある。これも「運」の要素が強いとみなされた。近年「打点」は「本塁打の副産物」のような評価になっている。セイバー系のデータを計算するうえで「打点」が組み込まれることはない。MLBでもNPBでも「打点王」は主要タイトルだが、MLBではその価値はほとんどないと言う評価だ。
主要3部門では「本塁打」だけが、高い価値があることになっている。
また本塁打を含む長打の率を示す「長打率」の評価も高い。
評価が高くなっているのは「出塁率」だ。四球を選ぶ能力=選球眼は、その打者の優秀さを示す指標となっている。

OPSが重視される
そして「長打率+出塁率」であらわされるOPS(on-base plus slugging)という指標が非常に重要視されている。
この指標は非常に単純だが、その後に考案された複雑な計算式を伴う高度なセイバーメトリクス系の指標と選手のランキングがほぼ同じになる。
MLB両リーグのOPS、RC(Run Create)、WAR3傑
アメリカン・リーグ
OPS
1位 ジャッジ(ヤンキース)1.159
2位 ソト(ヤンキース).989
3位 ウィット(ロイヤルズ).977
RC
1位 ジャッジ(ヤンキース)183
2位 ウィット(ロイヤルズ)150
3位 ソト(ヤンキース)147
WAR(Baseball Reference)※守備要素を含まないOffensive War
1位 ジャッジ(ヤンキース)11.7
2位 ウィット(ロイヤルズ)9.2
3位 ヘンダーソン(オリオールズ)8.5
4位 ソト(ヤンキース)7.9
ナショナル・リーグ
OPS
1位 大谷翔平(ドジャース)1.036
2位 マルテ(ダイヤモンドバックス).932
3位 オスーナ(ブレーブス).925
RC
1位 大谷翔平(ドジャース)174
2位 オスーナ(ブレーブス)122
3位 リンドーア(メッツ)113
WAR(Baseball Reference)
1位 大谷翔平(ドジャース)9.2
2位 リンドーア(メッツ)6.8
3位 マルテ(ダイヤモンドバックス)5.8
OPSには計算上、「打率」の数値が2回入っている。「安打は偶然の要素が多い」とされるが、打点のように完全に否定されるのではなく、一定の評価基準として残っていると言えよう。
RCは安打、長打、盗塁、三振、四死球、犠打、犠飛などの数値を組み合わせ、打点に近い数字にまとめたもので、新たな「打点」ともいえるが、WARをはじめとするセイバー系の新しい指標の出現で、あまり取り上げられなくなっている。
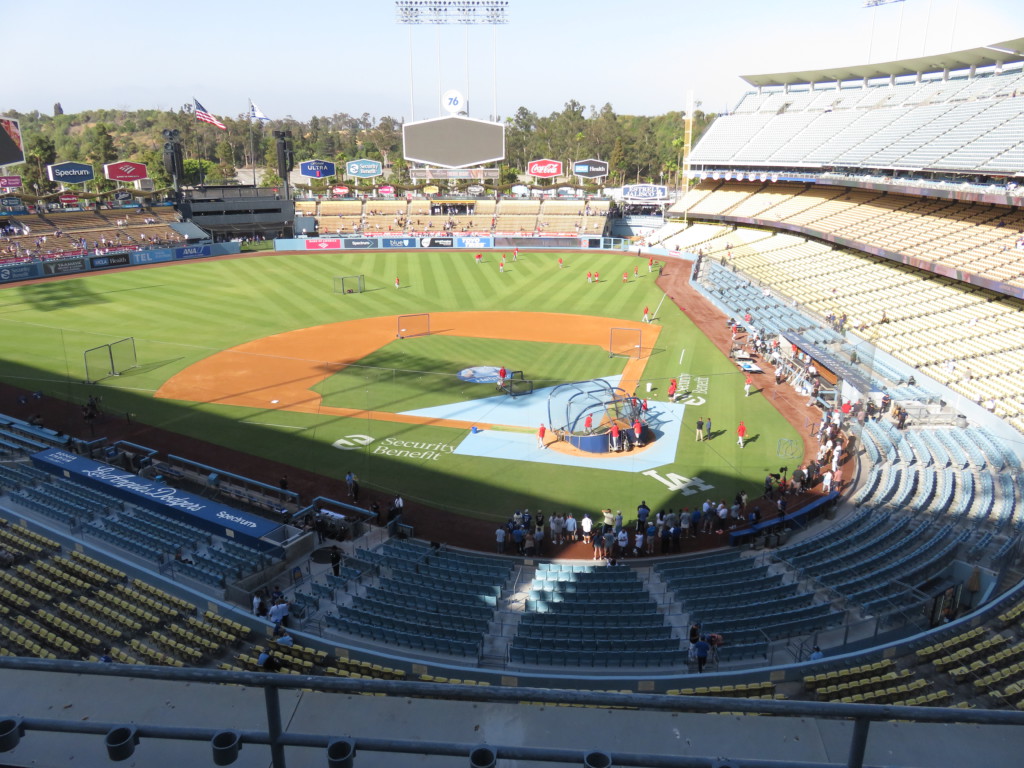
日本でも注目高まるOPS
9月14日時点でのNPBの両リーグのOPS3傑
セ・リーグ
1位 佐藤輝明(阪神).916
2位 森下翔太(阪神).803
3位 キャベッジ(巨人).777
パ・リーグ
1位 レイエス(日ハム).884
2位 杉本裕太郎(オリックス).777
3位 ネビン(西武).777
NPB球団関係者の間でも「OPS」を重視する人は多い。
NPBの公式サイトには載っていないが、打者に関してはOPSが最も注目される指標だと言えよう。











