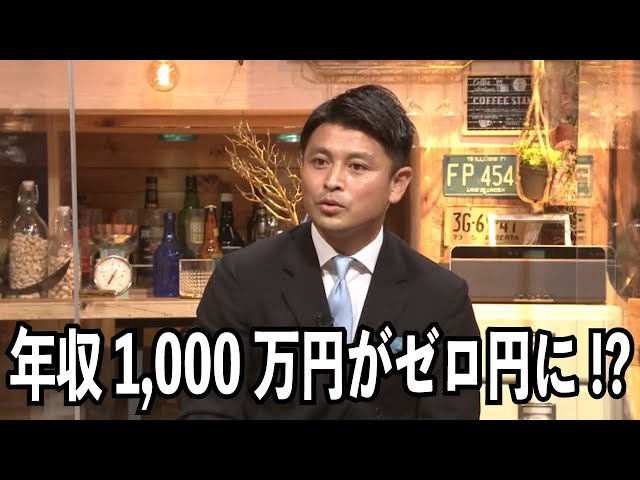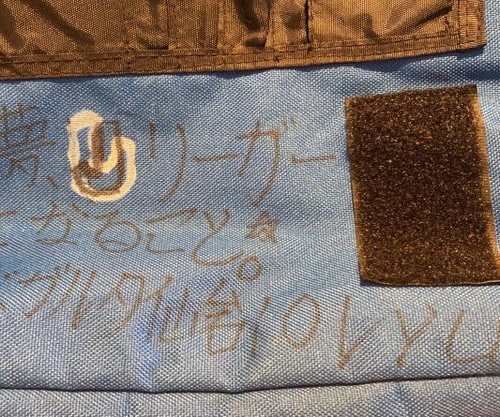「J1基準のクラブを、もう一度。」──佐藤謙介の挑戦と、レノファ山口の現在地

「今度は、背中を見せる側に」——
Jリーグ開幕から32年。地方クラブも、J1の頂きを本気で目指す時代に突入した。J1で戦い続けることのできるクラブが備える“J1基準”は、どのように育っていくのか。
J1昇格、そしてコロナ禍の特殊な状況ではあったが残留も経験した横浜FC。その過程でキャプテンとしてクラブを支えた佐藤謙介は、新天地レノファ山口FCで『J1基準のクラブづくり』への新たな挑戦を始めた。その現在地は——。〈全2回/後編〉(前編はこちら)

J1への挑戦と、理想と現実のギャップ
「変えていかなきゃいけない部分はたくさんある。でも、何から変えていくか…」
レノファ山口FCに加入して5年。佐藤謙介は、理想と現実のはざまで揺れていた。
本来であれば、横浜FCでスパイクを脱ぐ選択もあった。しかし、心を動かされたのは、レノファ山口FCというクラブの可能性だった。
山口県全域をホームタウンとするこのクラブは、Jリーグでも異色の存在だ。山口県サッカー教員団を母体とし、2006年に法人化。以降は地域の中小企業や有志の支援によって成長してきた。
注目すべきは、その成長スピードだ。JFLからJ3、そしてJ2へと駆け上がる中で、わずか1年でJ3からJ2昇格を果たした。その背景には、クラブ内部の柔軟な機動力と、地元自治体との連携があった。山口県の支援によりスタジアム、山陽小野田市と山口県サッカー協会の協力でJリーグのライセンス基準を満たすクラブハウスや練習場が短期間で整備されたのは象徴的だ。
地域密着を掲げるJリーグの中でも、最も“地域に根ざした”存在の一つ。それがレノファ山口FCだった。
「アットホームな環境があって、サポーターの応援も多彩で。正直、“すごいクラブだな”って思ったんです」
J1への挑戦が簡単ではないことは承知していた。しかし、可能性はある——そう感じさせる空気が、確かにあった。
そして、自分自身が年齢的にも“ベテラン”と呼ばれる立場になった今、横浜FC時代に三浦知良選手らが果たしていた役割を、次は自分が担う番だという気持ちもあった。
だが、現実は想像以上に厳しかった。
「こだわり」が文化にならない組織のもどかしさ
「やっぱり、どこかに“緩さ”があるんです。一つひとつのプレーへのこだわりが、まだ根付いていない」
横浜FCで当たり前のように共有されていた“プレーへのこだわり”。その一つが試合を決め、チームを変え、自分の価値を高める——そんな因果を理解したうえで行動できる選手が、レノファ山口FC(以下レノファ)ではなかなか育ってこない。佐藤はその現実に、もどかしさを感じていた。
もちろん、伝えようという努力はあった。監督も、ベテラン選手も、ピッチ内外でその重要性を繰り返し語った。しかし、意識の火はなかなか灯り続けない。数日、数週間は続いても、少し結果が出なければ、元に戻ってしまう。継続できない。その背景には、成功体験の乏しさがある。
「やっぱり人って、結果が出て初めて“ああ、こう繋がるんだ”って納得できる。そこまでいかないと、“続けよう”って気持ちも生まれてこない。レノファでは、その前に諦めが出てしまうことが多い。成長を止めてしまうんです」
人は体感がなければ変われない——それは、サッカーに限らず、どんな組織でも共通の課題かもしれない。
かつて、横浜FC時代の佐藤が監督やベテラン選手たちから教えられたように、「どれだけ信じて継続させられるか」は、クラブの文化をつくる鍵だった。
横浜FCでは、複数の経験豊かな選手たちが毎日、“継続”の価値を背中で示していた。その“日常の説得力”が、チーム全体の空気を変えていった。
だが、レノファには、その数が圧倒的に足りていない。
「去年でいえば、山瀬(功治)選手のような存在もいました。でも、やっぱり一人じゃ足りないんですよね」
文化を根付かせるには、語る人ではなく、“見せる人”が複数いることが必要なのだ。

ベテラン不在が引き起こす組織の不安定さ
だが、“見せる人”を数多くクラブにとどめておくこと自体が、地方クラブにとっては簡単ではない。
ベテラン選手は、若手よりもコストがかかる。連戦のなかでのパフォーマンス維持も難しくなる。限られた予算の中で、若手起用に傾くのは自然な流れだ。実際、レノファの平均年齢は2025シーズンで25.7歳。J1の20クラブと比較すると3番目に低い。
しかしその選択は、ときに“こだわり”の継続を損なうリスクも抱える。
「若い選手が中心になると、調子がいいときは勢いがある。でも、悪くなったときに“何を見て、どう立て直すか”という手がかりがない。方向性を示してくれる人がいないと、軸がブレやすくなるんです」
佐藤は、ベテランの価値をピッチ外にも見ている。試合に出ていなくても、ベテランがチームに与える影響は大きい。毎日の姿勢、言葉、佇まい——それらすべてが、若い選手に“基準”を見せる材料になる。
だが、今の立場だからこそ、その難しさも理解できる。
「出場していない選手に予算を割けるかというと、(レノファのような規模が大きくないクラブにとって)それは簡単じゃない。でも、そこが一番のジレンマなんです」
わかっている。だけど、それでも必要だと思ってしまう。クラブ文化をつくるには、そういう“無言の存在”が欠かせないからだ。
「プロの意識」を支えるはずの環境整備の遅れ
“プロとしての基準”が根付かない要因は、人材だけではない。
佐藤が加入初日に驚いたのは、選手たちの意識よりも、まず「環境」だった。
トレーニングルームに足を踏み入れた瞬間、目に飛び込んできたのは散乱した重り、錆びたダンベル、そして床に無造作に置かれたスパイク。アスリート用のバイクは1台だけ。練習後には“30分待ち、次は1時間待ち”という列ができる。諦めて帰る選手が出るのも無理はなかった。
「正直、トレーニング施設はもっと充実させないといけないです。ベンチプレスの重りも定位置がなくて散らばっていますし、ダンベルも錆びていて“いつの時代のものだよ”って思いながら使っていました。バイクは1台だけなので順番待ちが長すぎて、やめちゃう選手もいましたね」
スペースも足りない。朝のトレーニングルームは手狭で、選手たちが同時に動くと、体がぶつかりそうになる場面も少なくない。佐藤はふと、大学時代の施設を思い出した。
「正直、大学生のほうがいい環境でやってるんじゃないか? これで“プロ”と言えるのかって」

“食”と“休息”にも現れるJ2の現実
食事と休息の環境も深刻だった。
入団当初、練習後の食事は「各自で外食」が基本。練習は11時ごろに終わり、そこからケアをして食事に向かう。その時点で昼を回っている。
「それじゃコンディションは整わない、という声が出て、ようやく去年からお弁当が支給されるようになったんです。でも、まだ最低限のレベル。朝は当然出ないし、夜は各自で。若い選手なんか、家族のサポートもない中で本当に厳しいですよ」
二部練の日でも、クラブハウスには横になって休める場所がなかった。選手たちは一度クラブハウスを出て、一般利用者と同じ駐車スペースに止めた自分の車の中で、仮眠を取るなどでなんとかやり過ごしていた。
それは「リカバリー」と呼ぶには、あまりにも程遠い現実だった。シーズン終盤に増える怪我の一因なのでは、と疑問も湧く。 自分が“プロフェッショナルだ”と実感できる環境。その最も基本的な土台が、このクラブにはまだ整っていなかった。
地域密着の誇り、その裏にある“壁”
これには、J2昇格時の経緯も影響している。
現在クラブが使用している施設は、J2昇格時に急ピッチで整備されたものだった。Jリーグのライセンス基準を満たすため、山陽小野田市が手を挙げ、行政主導で整備に取り組んでくれた。トレーニング器具の一部は、山口銀行からの寄贈でまかなわれたという。
練習後の食事も、飲食店が支えている。栄養価を考え、タイミングを合わせ、懸命に準備してくれる姿があった。
「本当にありがたいと思っています。地域に支えられているクラブなんだな、と実感します」
そう語る佐藤の言葉には、感謝と同時に、ある種の焦りがにじんでいた。
「でも……どこかで、“うちはこういうクラブだから”って、この環境を変えていかない理由にしてしまっていないか、と思うこともあるんです」
アットホームな空気、手作りの支援、地域の熱意——それらはレノファ山口FCのかけがえのない“強み”だ。だが、その成功体験が、現状への満足感につながってはいないか。そんな問いが、佐藤の中に芽生え始めていた。
気づけば、レノファよりも後にJリーグ入りしたクラブが、次々と環境整備を進め、追い抜いていく現実も目にするようになった。
「このままで本当にいいのか?」
強みは、ときに変化を止める要因にもなる。過去の積み上げがあるからこそ、次に進む“痛み”をともなう変革には手が出しづらい。
「常に、“もっと良くしたい”という姿勢でいられるか? 変わらず、現状に甘んじずいられるか?」
佐藤の頭に、あの言葉が浮かんでいた。
「お前、それでいいのか?」
プロとしての日々を問い続ける言葉。いま、それはクラブ全体に向けて放たれているようだった。

「維新」のクラブにふさわしい、未来への挑戦を
2024年で佐藤謙介は現役を退き、ユニフォームの色を変えた。新たな肩書はアシスタントコーチ兼スカウト。ピッチの中から外へ——視点を変えて、クラブと向き合い始めた。
次に見据えるのは、J1という頂だ。
「まずは、プロとしての“環境”を整えること。その基盤がないと、選手もスタッフも“本気”になれない。クラブとして、スタッフとして、今に満足せずJ1を目指す姿を形にしたいんです」
レノファというクラブ名には、「維新(レノベーション)」という意味が込められている。かつて長州藩が時代を変えたように、この小さなクラブもまた、自らの手で常識を打ち破ってきた。佐藤は、その精神に、今の自分を重ねている。
「もちろん、財政面とか、難しいことはたくさんある。でも、それでも挑戦しなきゃいけないと思っています。これまで本当に多くの人に支えてもらってきました。その分、自分も“何かを残せる人間”でなきゃいけない。レノファ、そして山口のために、できることを全部やりたいと思っています」
現役時代、彼は数多くのプロフェッショナルたちの“背中”から学んできた。
その中にあった共通の姿勢。それは、「現状に満足しないこと」「常に、もう一歩前へ進むこと」。
いま、佐藤はその姿勢を、選手に、クラブに、そして地域に伝えようとしている。
スタッフとしても、新たな取り組みを始める。
歩みは小さくてもいい。時に道なき道でも、前へ進む。
維新の旗振り役に。佐藤謙介の挑戦は、これからも続いていく。

(取材・文/沖サトシ)